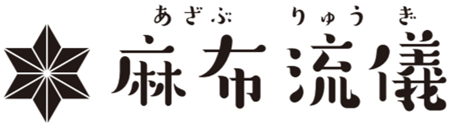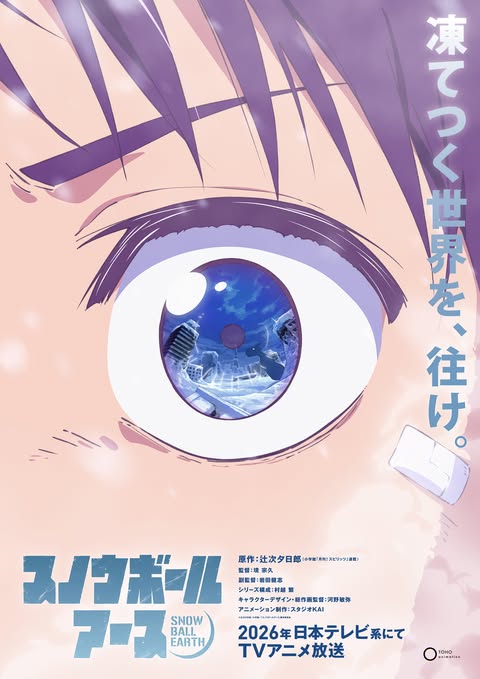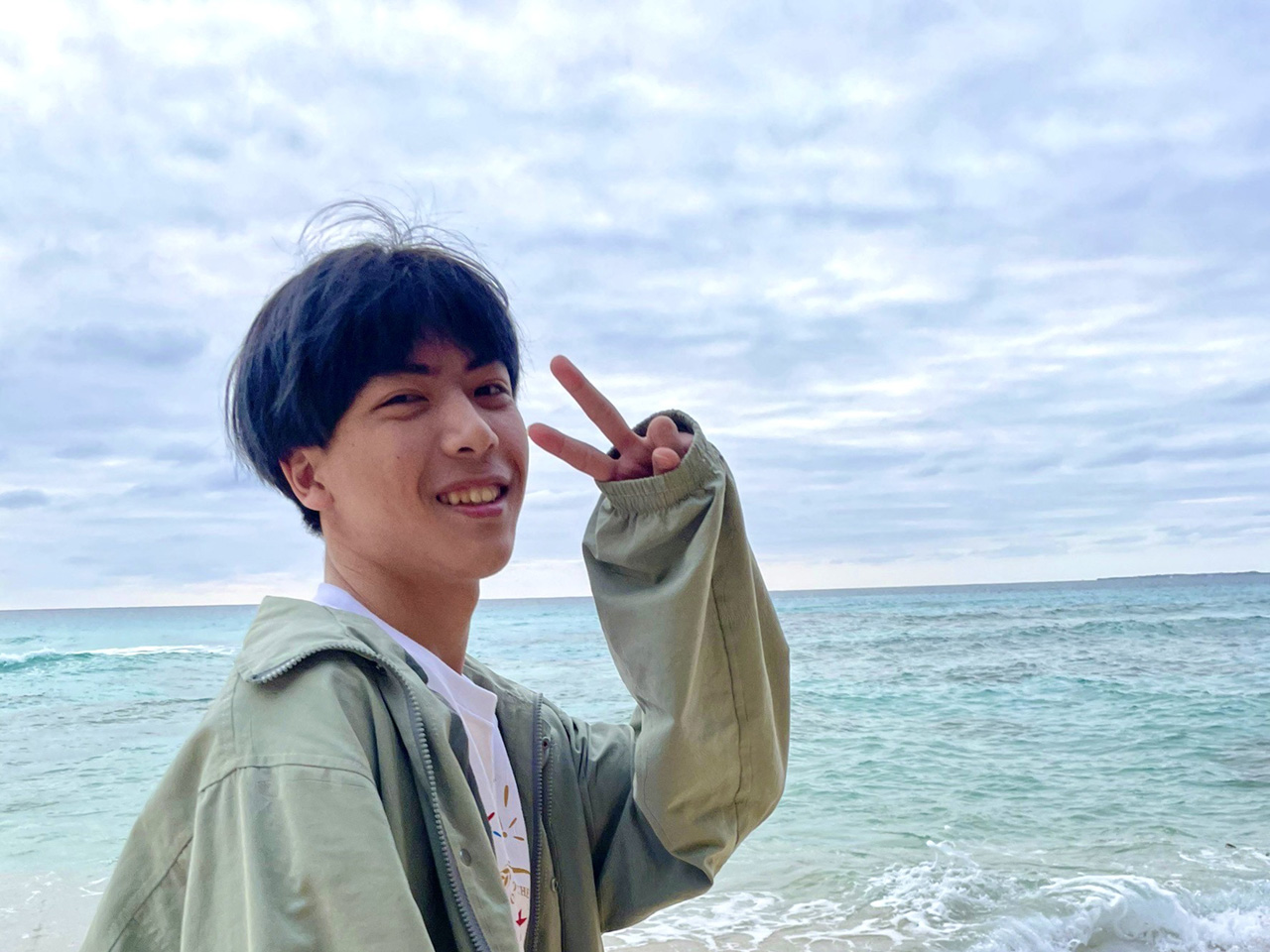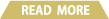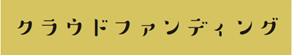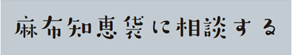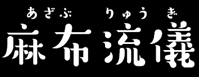2ステップの関係性。

イラストACより
ここ10年くらい意識してやめたことがある。「2ステップの関係性」の人と何かしようとすること、「2ステップの関係性」の人とために何かしようとすることをやめた。
「2ステップの関係性」はぼくの造語だ。
友人知人、家族に知り合い。
直接自分が関わりのある人を「1ステップの関係性」とする。
そして、友人知人のそのまた友人知人、みたいな人を「2ステップの関係性」とする。
たとえば友人知人から「知り合いがこれこれこういう症状なんだけど、どこか病院紹介して」と頼まれたとする。
そうした場合、かつては必死になってツテをたどってそこの医者に連絡をとって、受診できるようにした。
でも、今はそういうのはやめた。
あるいは何か勉強会や研究会みたいなものの講師をお願いするのに、かつてなら友人知人や知り合いに声をかけまくって、「誰か講師にいい人いない?」と探したりした。
でも、今はそういうのはやめた。
前者の行動、友人知人のそのまた友人知人を助けようとする行動は、良い人でいたい、正確には、友人知人に良い人と思われたいという気持ちに基づく。
でも、今はそういうのはやめた。
「2ステップの関係性」からの卒業の理由はいくつもある。
成長の段階で、「1ステップの関係性」の友人知人に十分恵まれた、というのが大きいと思う。
その上で、「2ステップの関係性」は不確定要素が多く、コントローラブルな要素が少ないのも理由だ。
たとえば一例目の、「友人知人のそのまた友人知人のために病院を探す」みたいなのも、「紹介してもらった病院、結局行かなかったみたい。なんかYahoo!口コミの良い民間治療のセンセイにかかったって」みたいなことが多すぎる。
あるいは二例目の「友人知人のそのまた友人知人に勉強会の講師を頼む」みたいなのも、「なんかよくわからないけど、あの人お前の勉強会の講師やったあとすごく怒ってたぞ」みたいなことがある。
いずれも「1ステップの関係性」なら直接「なんだよーせっかく紹介したのに病院行かなかったのかよ。今度、一杯おごれよ」とか「ごめんねーなんか不手際あったみたいで。今度、一杯おごるよ」で済む話だが、「2ステップの関係性」だとそうもいかずモヤモヤしたまま終わる。
待てよ、一例目の友人知人におごってもらうかわりに一例目の友人知人に二例目の友人知人におごらせればぼくは何もしないで済むな。
まあ地球上の人は最大6ステップの関係性を経ればみんなつながるという「スモール・ワールド仮説」もあるし、その仮説に基づく『私に近い6人の他人/Six degrees of separation』という舞台や映画もあるから、そう深く考えずにこれからもステップとか地団駄とかいろんなものを踏みながら生きていきたいと思う。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年10月4日を加筆修正)
好きを主軸に。

FIND/47 より 熊本県 水田
最近歳下の医学生と話す機会を得た。
彼らが口々に言うのは、「将来なに科医になるのがいいか迷ってて。AIとかもあるし、逆に手技のある外科とかのほうが生き残りやすいのかなって」だ。
医学生というのは、6、7年の大学時代に全ての科を学ぶ。医学生時代には専攻みたいなのはない。
今は大学卒業後2年間の研修期間があるが、昔は大学卒業の時に専攻する科を決めて教授のところに弟子入りのお願いをしに行った。医局に入る、いわゆる入局というやつだ。
将来なに科になるか悩む期間も増えたし、医療以外の分野で活躍する医師免許持ちもいるから選択肢も増えた。
選択肢が増えると、人間というのは逆に決められないものだ。
ましてやわが国の保険診療分野は先行き不透明。
僭越ながらアドバイスするとすれば、究極的には「好きなことをやれば」になる。
理由はいくつかある。
まず第一に、未来は完全には予測できない。
AIが進歩して内科医の代わりを務める日も来るだろうが、それがいつかはわからない。
世の中の風向きが変わって、AIは電気を喰うからやめようとなるかもしれない。
AIは個人情報をデジタルデータ化してグローバルに処理するわけで、その気になれば世界中のどこからでも誰かの個人情報(や会社の情報とか)をぶっこ抜ける状態だからやめようとなるかもしれない。
要は、外部要因というのは完全には予測不可能であり、しかも複数因子、マルチファクターが複雑怪奇に絡まり合うならなおさらである。
だが、「好き」という内部要因はそうそう変わらない。
だから予測不可能で可変な外部要因に基づいて未来を決めるのではなく、予測可能で可変性の低い「好き」という内部要因に基づいて未来を決めるのがよいのではないか。
〈最善の未来予測は、それを発明することだ〉(アラン・ケイ)
いくつか思うのは先人たちのことだ。
たとえばiPS細胞研究の山中先生は、当初整形外科医としてキャリアをスタートさせた。
残念ながら整形外科医は向いていなかったようで、基礎医学に転向し偉業を成し遂げたわけだが、重要なのはノーベル賞受賞者ですらキャリアスタート時には自分に何が向いてるかはわからないということだ。
あるいはスタジオジブリ宮崎駿監督。
今でこそ「世界のミヤザキ」として尊敬されているわけだが、あの人も外部要因が別であればまた評価も変わっていたかもしれない。
宮崎駿監督のキャリアの中で、アニメというものに対する世間的評価が逆風だった時代もある。
「アニメが犯罪を誘発する」みたいな世論があと一歩強く、アニメが強力に規制されていたら、宮崎駿監督は悪の親玉みたいな扱いだったかもしれない。
重要なのは、もしそんな状況でも、宮崎駿監督は地下にもぐって少女を主人公としたアニメを作り続けただろうということだ。
「好き」という内部要因は、強い。
わが国の保険診療分野は先行き不透明で、若き医学生が悩むのも無理はない。
だがその中でも「好き」を原動力に、未来を切り開いていってもらいたいと思う。
〈先が見えないからといって途方に暮れることはありません。どんなに自信を失っているときでも、その中でも自分にできることが必ず何かあるはず。〉(ショーン・ケイ)
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年11月10日を加筆・修正)
因果と縁。
「原因と結果。因と果で因果。
仏教では、因と果のほかに“縁”というのもありましてね。
因と果の間に“縁”があると考えます」
とある僧侶から聞いた。
その話を聞いたときは、「縁とか言い出したらなんでもありやんけ」と思った。仏罰が当たるといけないから黙っていたけど。
だが不思議なもので、月日が経つにつれて、なるほど“縁”というのはあるのかもしれないなと思うようになった。
“縁”とはなんだろうか。
オカルト的なもの、スーパーナチュラルなものをできるだけ排して考える。
つらつら考えるに、“縁”とはランダム性かもしれない。
生命を細菌やウイルスから守る免疫機構の一部である抗体は多種多様で、その数はどう考えても遺伝子の組み合わせより多いという。
なぜ有限な遺伝子の組み合わせの数を超えて、無限に近い抗体が作り出されるかは長年に渡り医学のナゾの一つだった。
それに対しアンサーを出したのが利根川進氏で、遺伝子と抗体は一対一対応ではなく、遺伝子がある程度ランダムに組み合わさって抗体の設計図となることで、多くの組み合わせが生まれるのだという。
医学生時代に授業で聞きかじった話で、なにしろ劣等生だったから記憶もあいまいだ。
将来この麻布流儀のネタになるってわかっていればもっとしっかり授業を聞いていたのだが仕方がない。なにしろその頃はまだ麻布流儀は無かったからな。
遺伝子の組み合わせという“因”が、抗体という“果”を生み出すまでに関与するランダム性。これが“縁”ということではないか。
名作映画『おくりびと』の原案である青木新門氏の小説『納棺夫日記』。
映画『おくりびと』を因果の“果”とすると、『納棺夫日記』は間違いなく原因である“因”である。
『納棺夫日記』が無ければ、『おくりびと』は生まれなかった。
だが、『納棺夫日記』という“因”があれば、必然的、自動的に『おくりびと』は生まれただろうか。
『納棺夫日記』はお読みいただければわかるとおり、非常に地味で内省的、後半は物語の形から離れ、いわば哲学的モノローグとなっている。
当初、『納棺夫日記』は自費出版に近い形で世に出され、初版は500部から2500部程度であったという。
そんな形で世に出た、いわば地味な一冊の本がまわりまわって1人の読者の手に届く。本木雅弘氏である。
インドへの旅の中で生と死を見つめた若き本木雅弘氏は、友人から勧められてこの本を手に取り、その一節に心をつかまれた。
<蛆を掃き集めているうちに1匹1匹の蛆が鮮明に見え始めた。畳を必死で逃げている蛆もいる。柱をよじ登っているやつまでいる。蛆も命なんだ。そう思うと蛆たちが光って見えた>
本木雅弘氏は、その後何年もかけて周囲を説得し、『おくりびと』を映画化した。
500〜2500部という限られた本が世に出、それが一人の読者に届くというのは“縁”であろう。
もしあの時、この本でなくほかの本を本木雅弘氏が手に取っていたら、と思うと、“縁”というものの一部はやはりランダム性な気がする。
そしてまた、“縁”というのはランダム性だけではない。
『納棺夫日記』を映画化したい、という本木雅弘氏の強い意志が無ければ、やはり『納棺夫日記』という“因”は『おくりびと』という“果”は生まれなかっただろう。
というわけで、因果を結ぶ“縁”。
縁というのは、ランダム性と人間の意志ではないかと思った次第である。
それではまた。良い1日を。
縁があったらお会いしましょう。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年10月17日を加筆・修正)
「ねたみ」考。
およそ世の中のモノには良い面悪い面両面あって、一見悪いことのように見えても別の面から見るとポジティブな働きをしていることもある。
「怒り」などはその代表で、怒ってる人を見るとまわりはおっかないけれど、悪や不正に対する「怒り」もある。そうした義憤や公憤が社会悪を克服する原動力となることもあるので、「怒り」の感情は実は大切である。
だがしかし、一個だけ悪い面しかない感情がある。
それはねたみの感情、「怨望」である。そんなことを福澤諭吉が書いている(福澤諭吉・著、齋藤孝・訳『現代語訳 学問のすすめ』ちくま新書二〇〇九年 p.163-175)。
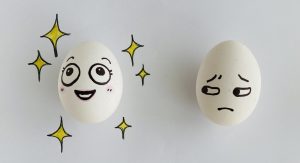
photoACより
ねたみの感情は、ただひたすらにネガティブだ。
〈怨望は、働き方が陰険で、進んで何かをなすこともない。他人のようすをみて自分に不平をいだき、自分のことを反省もせずに他人に多くを求める。そして、その不平を解消して満足する方法は、自分に得になることではなく、他人に害を与えることにある。〉(上掲書 p.165)
個人的には、空を飛ぶ鳥を眺めて暮らす日々でこのねたみの感情というのはどこかへ行ってしまった。「鳥のヤツらは飛べていいなあ」とねたんでも仕方のないことで、ただ捕まえて羽根をむしって喰うだけである。
このねたみの感情がなぜ生まれるか。福澤諭吉はこう分析する。
〈(略)怨望は貧乏や地位の低さから生まれたものではない。ただ、人間本来の自然な働きを邪魔して、いいことも悪いこともすべて運任せの世の中になると、これが非常に流行する。〉(p.168)
「親ガチャ」などという言葉が日常的に使われ、ねたみがあふれるSNS時代にこの言葉を思うと味わい深い。
いつの世も生まれついての不公平はゼロにはならないが、それでもなお自助努力で多少はなんとかなる仕組みにしておかないと社会にねたみが蔓延するのだろう。
ねたみの生まれにくい社会にするというのは為政者に任せるとして、個人としてはどうするべきか。
まず第一に、「ねたまないようにする」というのは机上の空論である。そんなのムリっす。
ねたみという感情の悪いところは、不平を言うばかりで行動に移さないことである。だから行動に移す。
もちろん「無敵の人」路線はいけない。
だがねたみの対象となる人をよく観察し、そのねたみの源、専門用語でいうところのネタミゲンを研究する。
そうしてネタミゲンの良いところをマネしたり、悪いところをマネしないようにする。
万物すべてを我が師と考えるのだ。我が師にも教師と反面教師がいるので、どうぞお好きなほうをお取りください。
自分の人生は自分のものなので、より良い人生を送れるようねたみすらなんらかの原動力にしてしまうしかないだろう。
合言葉は、「こ・の・ね・た・み・は・ら・さ・で・お・く・べ・き・か」である。メラメラメラ。
(『カエル先生 高橋宏和ブログ』2025年1月20日を加筆・修正)
「終活」があれば「中活」もある。
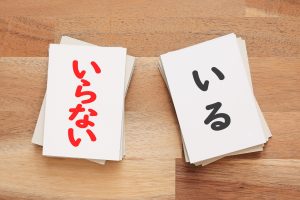
photoACより
「終活」というものがあるならば、「中活」というものもあるのではないか。そんなことを考えた。
wikipediaによると、自分の人生の終末に向けていろいろと整理をする「終活」という言葉が考えられたのは2009年だという。その年の週刊朝日で終活の特集記事が数ヶ月に渡って組まれた。
ありのままを書くと、いわゆるミドルエイジ・クライシスとどう付き合うかがこの数年のテーマだ。
自分はこれからどう生きていったものか。そんなことを考えるなかで、齋藤孝氏のこんな言葉に出会った。
〈(略)私は50歳になって、本を捨てられるようになりました。これまで相当な量ーおそらく何千冊という単位ーを手放してきました。〉(齋藤孝『50歳からの孤独入門』朝日新書 平成30年 kindle版80/138)。
齋藤孝氏ほどの多読多作の方でも、50歳の若さで蔵書を整理し始めるのかというのが驚きであった。
これを読んで積極的に身の回りの細々としたものを整理し始めたのが数ヶ月前。実に多くの発見があった。
やや偏執狂的に、毎日毎日少しでもいいからものを捨てる。本一冊CD一枚、はるか昔いただいた名刺一枚チラシ一枚でもいいから毎日捨てる。
そんな日々を送っていると、たしかにココロの健康によいのである。
スピリチュアルなことを抜きにして考える。
昔、滋賀県の工場で暑さのなかロクセラム・アムマットの粉塵に悩まされながらジンキーを塗っている頃、工場のラインが故障で止まるたびに身の回りの掃除を命じられた。
「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5S活動というヤツで、当時はラインが止まったら休ませてくれよと思ったがあれはあれで意味がすごくある。
今パーソナル5S活動をしてみると、隙間時間に整理整頓をし続けると、忙しい時の探し物が減る。
なにしろ物が減ってるから、大事なものがすぐ見つかる。
また、5S活動のウラの目的は、ヒマな時間を無くすと余計なことを考えたりしなくなるというのもあるのであろう。
思えば自衛隊の富士学校に体験入隊した時も、スキマ時間があれば常にブーツを磨くよう指導されたものだ。
人間、ヒマな時間が出来ると余計なことを考えて悩んだりする。
また、モノを整理して捨てていくと、不必要なものに時間と気力を取られなくなるとともに、整理の過程で取っておくべき「自分が本当に大切にしたいもの」を再発見する。
認知症のケアの中で「回想法」というのがあって、これは認知症患者さんの過去を積極的に振り返ることでアイデンティティを確認してココロの安定を図るというものだが、ものを整理する過程で「自分が本当に大切にしたいもの」を再発見することで同じような効果があるのだろう。
終末期にはまだ早い中年期に、さまざまなものを整理整頓して人生後半戦に備える、中年期活動、略して「中活」というのもあるのではないか。
そんなわけで、これからミドルエイジ・クライシスを迎えられる皆様におかれましては、「中活」というのをしてみてもよいかもしれません。
〈どのように靈魂がその肉體に住んでいるか見たくおもうひとは、どのようにその肉體がその日常の住居を使用しているか觀察するがよい。つまり、住居に秩序がなく亂雑である場合には、その靈魂の支配する肉體も無秩序で亂雑であるだろう。〉(『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上)』岩波文庫p.58)
住居を整え肉体を整えることで、ココロを整えるやり方もあるのだろう。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年8月1日を加筆修正)
音楽の好みは13~14歳に決まるという話。
「音楽の好みは14歳の時に聴いていた曲に左右される」という説がある。
ネタ元を掘っていくと、2018年2月10日配信のThe New York Timesの記事が元らしい。
Spotifyのデータを解析すると、男性は13歳から16歳の間、女性は11歳から14歳の間に聞いていた曲が音楽の好みに影響するという。
脳の可塑性などなどの理由もあるのだろうが、非常にわかる気がする。
音楽と青春期について酒井順子氏がこんなことを書いている。
〈音楽等によって刺激される懐かしさは、「その曲がヒットしていた頃の自分」が喚起されるからこその感情であるわけですが、その頃の自分が「未完成」であればあるほど、懐かしさは強まるようです。〉(酒井順子『ガラスの50代』講談社 二〇二二年 kindle版40-41/205)
13歳14歳の頃が懐かしいからその頃の曲を聴き続けるわけでもなかろうが、「未完成」の頃の曲ほど懐かしい、という指摘は美しい。
大人になるだけで人間として完成するわけでもないし完全体になるわけでもない。
しかし大人になればそれなりに、仕事だのなんだので空白は埋まってゆく。
10代の、不完全で未完成で空白だらけでそのくせ溢れんばかりの承認欲求と万能感と劣等感と無力感とその他もろもろがごった煮になったあの時期。何者かになりたい何者にもなれないという思い。真夜中の煩悶。
「自分」というパズルは足りないパーツばかりで、どこかにあるかもしれない足りないパーツを求めて音楽や小説や映画や深夜のラジオやテレビや今だと動画を漁りまくる。漁っても漁っても決して癒えない心の渇き。
そんな時期に貪るように聞いた曲が、生涯に渡る音楽の好みに影響を与えるのは当然かもしれない。
この夏、空白を埋めるべく、足りないパーツを求めて音楽に漫画にアニメに小説に動画に溺れる全ての13歳14歳に祝福を。
どうか良き旅を。
素晴らしい出会いがあることを祈ります。

photoACより
耳鳴りと難聴と夢想家の話。

photoACより
「耳鳴りというのは」
耳鼻科医が言った。
「難聴の裏返しなんですな。
聴力検査のグラフです。
ほら、左耳の、特に高い音が聴こえにくくなってる。キーンという高い金属音みたいな耳鳴りがするんですよね?そのぶん、高い音が聴こえなくなっているんです」
ふんふんとうなづきながら、僕はさっき受けた聴力検査を思い出した。
小さな部屋。完全防音。ヘッドホンから様々な高さと大きさの音。音が聴こえたらボタンを押す。音を聴くことに全力。耳鳴り。
ライカ。
ライカはどんな気持ちだったのだろう?
スプートニク2号に乗せられて、身動き取れないまま宇宙へ飛ばされたソ連の犬。
もし今、聴力検査室が宇宙に飛ばされたら、ライカの気持ちがわかるだろうか?
音ガ聴コエタラ手元ノぼたんヲ押シナサイ。押シナサイ。
ぼくは耳を傾ける。一生懸命に。宇宙空間で。
「というわけで、耳鳴りと難聴は裏表なんです。よろしいでしょうか?」
耳鼻科医が言い、ぼくは宇宙から帰ってくる。
ライカも帰って来られればよかったのに。
「ええと。非常に面白いと思います。なんというか」
説明の間に宇宙に行っていたことに気づかれないよう、ぼくは言った。
「ええと。なんというか。
ええと。先生、一つ聞いてよろしいでしょうか?」
「なんです?」
耳鼻科医の目からすっと光が消えた。
「難聴がするから耳鳴りがするんでしょうか。耳鳴りがするから難聴がするんでしょうか」
「どういうことです?」
「つまり、なんというか、現実の音が聞こえなくなったから、埋め合わせをすることように幻の音、つまりは耳鳴りのことです、が聞こえるようになるのか。
それとも幻の音、耳鳴りが聞こえるから現実の音が聴こえなくなるんでしょうか?」
「面白いですね」
面白くなさそうに耳鼻科医は言った。お腹でも痛いのだろうか?
「個人的には興味深いと思います。
だがきちんのお答えできるほどの時間は無いかな。次の患者さんもいるし」
興味も無さそうに、耳鼻科医は言った。
その表情を見て、やっとぼくは悟った。やっぱりこの人はお腹が痛いんだな。
「それにどのみち」
耳鼻科医は小さな小さなため息をついた。見えないくらいの。
「耳鳴りは手強いのです」
「ありがとう先生」
ぼくは席を立った。
誰にでもお腹の痛い時はある。早くこの人を解放してあげなければ。
「よい一日を」
「お大事に。次の方どうぞ」
待合室に座って考えた。
耳鳴りと難聴、どっちが先なんだろう?
夢想家、という種族がいる。
ああでもないこうでもないと夢想しながら人生を過ごす。
そしてこの世を去るときに、「人生は夢まぼろしのごときなり」って言う。
無理もない。夢を見ながら人生を過ごしたんだから。
夢想家には2種類いる。
夢想するから現実が見えない者と、現実が見たくないから夢想する者と。
まあいいや。
どのみち、夢想だって手強いのだから。やれやれやれやれ。
「お会計できました、タカハシさん」
夢想と耳鳴りと処方箋。忘れずに、薬局に行かなきゃ。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年5月27日を加筆修正)
いわゆる”脳科学”を批判する。2
いわゆる“脳科学”、「最新の脳科学によれば人間とはこうだ」みたいなエセ科学のブームについて嫌悪感と警戒感を抱いている。嫌悪感と警戒感の理由については前述の通り。
さて、いわゆる“脳科学”の多くは、ごく限られた条件下の限定的な科学的発見を、恣意的につまみ食いし自分の思いつきや経験論に宣言なく無理やり当てはめ、仮説ではなく「ご宣託」として押し付けてくるものである。
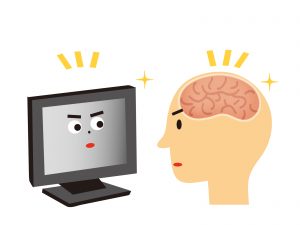
イラストACより
では、そんな胡散臭いものがこれだけ長きに渡ってブームになっているのはなぜか。言葉を変えれば、人々はなぜいわゆる“脳科学”に心惹かれるのか。
複雑怪奇、不可解で理不尽な人間という存在や、社会というものを単純明快な「最新の脳科学」とやらでわかったものにしたいという欲求はあるだろう。わからないものをわからないまま付き合っていくのは知的スタミナを要する。それよりは「最新の脳科学」によればこうだよね、としたり顔できたほうが楽だ。
精神科医の斎藤環氏は別の見方を提示している。
“脳科学”が多くの日本人に受けるのは、〈脳が様々な問題を外在化する装置になっている〉からではないかという仮説だ。
斎藤氏は佐藤優氏との対談でこう述べる。
〈斎藤 自らにとって不都合な事象を認識した時に、それを心で受け止めようとすると、自分の内なる問題、自己責任になってしまうこともあるでしょう。しかし、脳のせいにすれば、それはまあ生まれつきなのだから自分の問題ではないんだ、ということにできる。そういう不思議な思考回路ができている感じがするのです。
佐藤 自分がこんな人間なのは、自分をコントロールする脳内分泌物のせいだ。もっと言えば、そういう脳のつくりを遺伝させた親のせいだ。だから自分に責任はない、恨むべきなのは親なのだー。〉
(〈〉内は佐藤優・斎藤環『なぜ人に会うのはつらいのか』中公新書ラクレ2022年 p.78-79)
なんでもかんでも自己責任を押し付けられる現代社会において、“脳科学”は「あなたのせいじゃないよ、ぜんぶ“脳”のせいだよ」と甘く囁く。
“脳科学”は「問題の外在化」をすることにより現代人を自己責任から解き放つ。だから“脳科学”はブームになるのではないか、というのが上掲書・上掲箇所における斎藤環氏の考えである。
“脳科学”の本質が「問題の外在化」であるとすれば、全く別の側面がある。
斎藤環仮説が正しいとすると、知的良心を捨てることができれば『人のせいにする脳』という本を書いたり、あるいは「問題の外在化」にあらがうような『NOと言える脳』という本を書いたりできるかもしれない。
”脳科学”ブームがいつはじまったのか。ふりかえってみると、総胆管末端筋の研究で学位を取ったという春山茂雄氏の『脳内革命』(1995年)あたりだろうか。以来ずっと”脳科学”ブームである。
なぜ“脳科学”がそれほどまでにウケるのか。
斎藤環氏は、“脳科学”は問題を「外在化」し、自己責任論から読者を解放してくれるからウケるのではないかと指摘した(前述)。
あなたが抱えている問題はあなたのせいじゃない、脳のせいだ。脳のホルモンが前頭葉がシナプスがこれこれこうだから問題は起こるのだ。あなたのせいじゃないあなたのせいじゃない脳のせいだ脳のせいだあなたは悪くないよと“脳科学”は甘く囁く。だから“脳科学”は人々の心をとらえるのだというのが斎藤環仮説だと思う。
この仮説を考えていて面白いことを発見した。
“脳科学”が問題を「外在化」し、問題は自分の「外部」にあると示すというのがここでの斎藤環仮説の本丸だと思う。
だが面白いことに、多くの読者が「外在化」された問題を「仕方ない」と思うのと対照的に、一部の読者は問題が「外」にあるからこそコントロール可能と思うのではないか。
たとえばイーロン・マスクのような人物は、問題が「外」にあればあるほどコントロール可能と考える(のではないか)。
彼のような人物は、我がことよりも「外部の問題」こそコントロール可能、解決・克服可能と考えて燃える。
そんな人たちにとっても、“脳科学”が問題を「外在化」させることで「“脳”をハックしてうまいことやろう」と意欲をかきたてられる。
すなわち、“脳科学”が問題を「外在化」させることで、「外部」の問題はコントロール不可能と思う多くの人たちも、「外部」の問題こそコントロール可能と思う少数の人たちも真逆のアプローチで“脳科学”を受け入れる。そんな構造があるのではないか。
“脳科学”は、前者には癒しと慰めを、後者には励ましとやる気を与えてくれるのだろう。
まあここらへんになってくると「理屈とポストイットはどこへでもくっつく」というヤツで、どうとでも言えるのだが、「“脳”をハックしてやろう」という見方で“脳科学”をとらえる一群がいるというのは悪くない見方だと思う。
いずれにせよ、誰かが言っていることを無批判に受け入れ信じ込むというのは科学ではない。
眼の前の事象や誰かが唱えている仮説を懐疑的・批判的に検証して、検証に耐えるものだけを「ひとまずの真実」として受け入れるのが科学なので、”脳科学”とは科学的につきあっていくべきだろう。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年3月11日、3月12日を修正加筆)