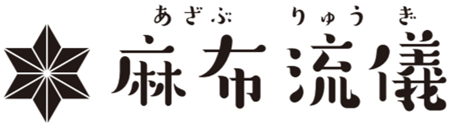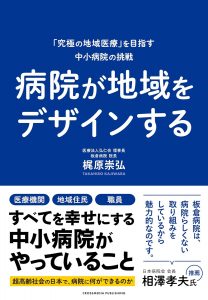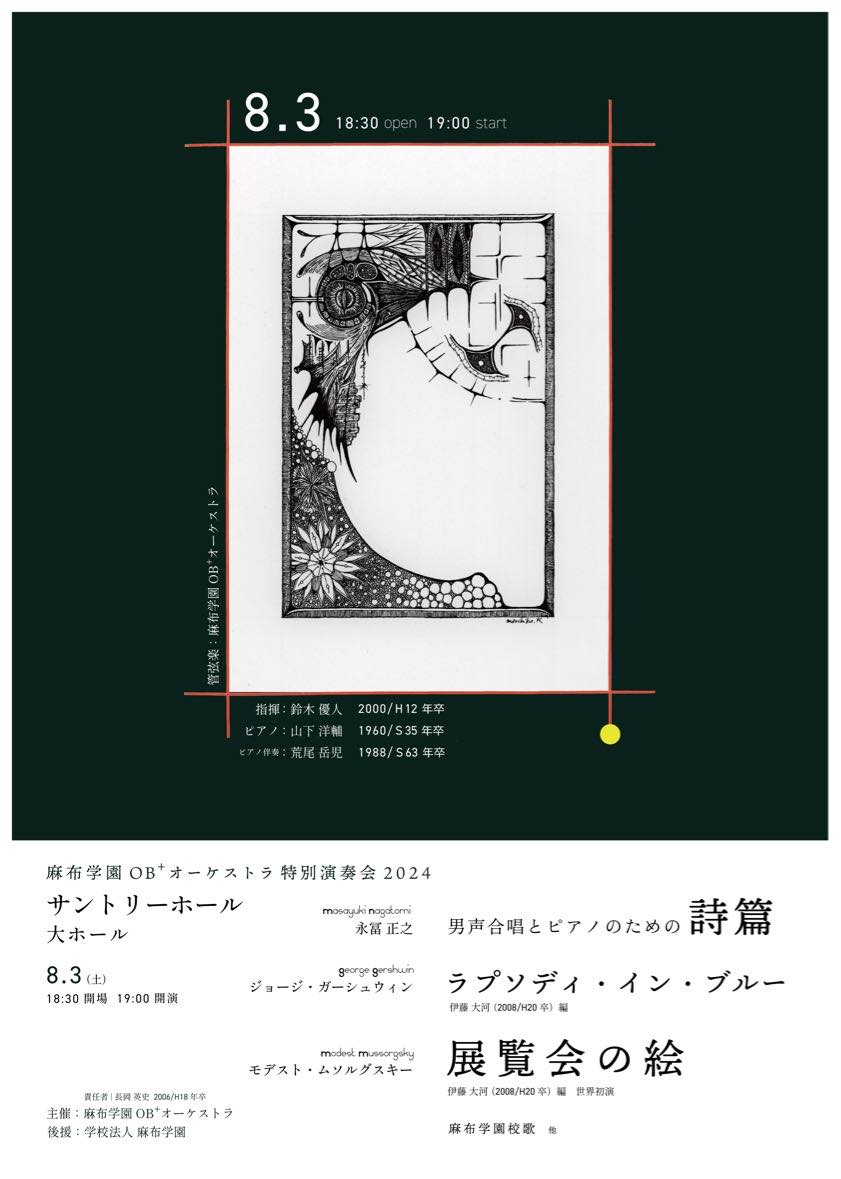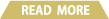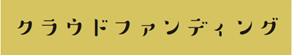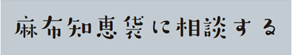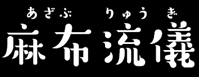いわゆる”脳科学”を批判する(その1)

photoACより
いわゆる“脳科学”、「最新の脳科学によれば人間とはこうだ」みたいなエセ科学のブームについて、嫌悪感と強い危惧を抱いている。
嫌悪感の理由を述べる。
科学とは健全な懐疑主義に基づき、観察と記録により仮説を打ち立てそれをほかの研究者とともに検証を重ねて少しずつ真実として認められていく、あるいは検証により仮説が否定されたら棄却し次へ進むものだと考えている。この際、仮説は反証可能な形で提示されなければならない。
これに対し一部の“脳科学”では、自分の思いつきや経験談を、科学研究の知見を恣意的につまみぐいし拡大解釈に拡大解釈を重ねて「最新の脳科学ではこうだ」と反証不可能な形で「ご宣託」として押し付ける。
それは科学者として不誠実であろう、というのが“脳科学”に対する嫌悪感の理由だ。
こうした「最新の研究では人間というものはこうだ」という論が、たとえば脳科学評論家とか科学ジャーナリストという肩書きでなされるなら個人的には受け入れる。
“脳科学”ではないが、そうしたスタイルで成功した物書きにマルコム・グラッドウェルがいるが、マルコム・グラッドウェルはあくまで「ジャーナリスト」の肩書きで売っているので「おもしろ科学読み物」として読者はとらえるだろう。
グラッドウェルのスタイルを模倣する物書きはグラッドウェリアンと呼ばれるが、もしグラッドウェリアンが「科学者」の肩書きを印籠にして自分の思いつきレベルのものを「最新の脳科学では人間とはこうだ」みたいに押し付けてきたら、警戒が必要だ。
危惧の理由は、こうしたエセ科学が悪きオカルトの「ゲートウェイドラッグ」の役割を果たすのではないかということだ。
「軽い」違法薬物に手を出すと、一部の人はより「強い」薬物へと進んでしまう。
こうした「強い」薬物への入り口となるドラッグを「ゲートウェイドラッグ」と呼ぶという。
エセ科学を盲信した人の一部が、悪きオカルトやエセ・スピリチュアルに進んでしまうのではないかというのが危惧の理由である。日本ではオウム真理教の例がある。
オカルトもスピリチュアルも、節度を持って楽しむぶんには害が少ないし、時に人生や社会のいろどりにはなると思う。
だが、オカルトやスピリチュアルにどっぷりハマると、抜け出せなくなる。
そうなってからでは遅いので、「ゲートウェイドラッグ」である“脳科学”の段階で警鐘を鳴らしておくべきだと思うのだ。
エセ科学、“脳科学”、オカルトにスピリチュアルは用法容量を守って健全に楽しまないといけない。
付記)
きちんとしたニューロサイエンティストの集まりである日本神経科学学会の指針を下に示す。2の「非侵襲的研究の目的と科学的・社会的意義」を読むと、いわゆる“脳科学”ブームに対して正統な研究者が苦々しく思っていることがわかる。
[神経科学の発展のために] 「ヒト脳機能の非侵襲的研究」の倫理問題等に関する指針(2022版)
https://www.jnss.org/human_ethic?u=27085f6771fe6499dabcee2cc32940df#link_b
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年3月10日を加筆・修正)
幸せには外部要因と内部要因がある。
あまり意識されていないことだけど、幸せには外部要因と内部要因がある。
外部要因には富や名誉や地位なんかがあって、それらを子供たちが獲得できるように親たちはしゃかりきになるけれど、もしかしたらそれ以上に大事なのが内部要因だ。

photoACより
内部要因は言い換えれば「心のあり方」。
「心のあり方」がうまく育っていないと、外部要因がどれだけそろっても幸せになることは難しい。
「心のあり方」は、言ってみれば幸せを感じる能力なのである。
幸せになるための「心のあり方」とはどんなものであろうか。
昔読んだ交流分析(Trasactional Analysis; TA)の本がヒントとなった。
今から20年も前に読んだ本で、現在の精神医学/心理学からはオールド・ファッションかもしれない。
少々うろ覚えだけど、こんな考え方だった。
すなわち、最も安定した心のあり方は、
I’m OK, You’re OK.
自分もOKな存在で、他人もOKな存在である、という認識。
自分はOK、他人はNGだと傲慢になる。
自分はNG、他人はOKだと卑屈になる。
自分もNG、他人もNGだと――たぶん、生き地獄だろう。
自分もOK、他人もOKな心のあり方を育んでいくにはどうしたらよいか。
おそらく、そこで重要になってくるのが、「無条件の愛情」だ。
「勉強ができるから」、「外見がかわいいから」、「歌がうまいから」-なにかができるから、自分は愛される、という「条件付きの愛情」ではなく、自分自身は存在するだけで無条件に愛される、という体験を十二分にして初めて、子供は自分自身がこの世に存在していいのだと思えるのだろう。
「条件付きの愛情」の中で育ってしまうと、自分自身の存在が許されるのは、「勉強ができる」、「外見がかわいい」、「歌がうまい」といった条件が満たされるときだけになる。
そういった心のあり方を獲得してしまうと、まさに底無し沼だ。
どれだけ富を獲得しても満ち足りず、どれだけ出世しても飽き足らず、どれだけ異性から愛されても無限に愛を求め続けてしまう。
ほんとうに必要なのは、ただ一つ、自分の存在を無条件に肯定してくれる「yes」という言葉だけなのに。
だから人は、白い脚立にのぼり、ぶら下がった虫めがねを手に天井にyesの文字を探す。
名曲とダンスで世界を魅了しながらも何十回も自分の外見を変え続け、何十万の歓声を浴びながらも健やかな眠りを得られなかったマイケルが求めたものも、きっと自分自身を全肯定してくれる、yesの一言だったのだろう。
その無条件の愛情、無条件のyesを与えてあげられるのは、子供たちの親をはじめとする周囲の大人たちだ。
人生早期のそのyesさえあれば、たぶんそこから何十年か子供たちはやっていけるのだと、ぼくは強く信じる。
「それでも人生にイエスと言う」ためには、はじめにまわりの大人たちが教えてやらなければならないのだ。
ことほど左様にぼくはyesと言うことに重きを置いている。
そんなわけで、もし将来、博多でクリニックを開くことがあったら、キャッチフレーズは
Yes!中州クリニック
にしようと思う。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年2月3日を加筆修正)
不易と流行、古典と現代。
不易と流行の不易に触れたくて、細々と古典を読んでいる。
原著で読めるほどの力は無いから邦訳や解説書を読むのだが、多くの古典の名著の母国語訳が千円から数千円で手に入る出版大国・日本には心から感謝である。

photoACより
わからぬながらも古典を読んでいると、数千年前の人が考えた思想や言葉が、時を越えて胸に刺さるのを感じる。名著の名著たるゆえんだが、数千年前に吐かれた言葉の矢が現代人の心に刺さるなんてことが、なぜ起こるのだろうか。
古代の賢人たちの個々の素晴らしさはひとまず置いておくとして、まずはこうしたことが考えられる。
数千年から一万年近くの人類の歴史のなかで、ほんとうに無数の思想や言葉が生み出された。
その中で後世の多くの人に刺さる思想や言葉だけが生き残った。
刺さらぬ思想や言葉は忘れ去られたからら、残った思想や言葉は立派なものだけとなった。思想や言葉の生存バイアスである。
そしてまた、つらつら考えるに、生き残る思想や言葉というものは、人間の身体性に根ざすものが多い気がする。
どんなに社会体制が変わっても科学や技術が進歩しても、人間の身体性はあまり変わらない。
朝になれば目が覚めてなんだかんだと動き回る。動き回れば腹が減る。腹が減って飯を食えば美味かったりまずかったり。腹一杯になれば眠気にも襲われるだろう。
長い年月には恋をしたり学んだり学んでも忘れたり、そうこうしているうちに歳を取って老いて死んでゆく。
そんなのは何千年も変わらない。
人間の愚かさダメさ賢さ尊さの多くは、心も含めた身体から生まれいづる。
そんな変わらぬ身体に基づき出てくる様々な事象が絡まり合いそれぞれの時代は織りなされる。だから数千年前に吐かれた思想や言葉が身体性に根ざしたものであれば、現代人にも刺さる可能性が高まる。
もっとも、科学や技術により身体性も拡張するから少しずつ事情は変わってくる。
身近な例でいえば、数十年前なら「あの人はなんでも知っていて、まるで“歩く事典”だね」みたいな褒め言葉はまだ使われていたが、どこにいても一瞬であれこれ検索できるようになったネット時代はそうしたことは言われなくなった。記憶力や知識と言った脳の機能が、ネットにより拡張したおかげである。
これからも様々な身体機能があれこれ拡張し、それによって語り継がれる古来の思想や言葉も変わってくるだろう。
だがまあ変わらないのは、どんな状況になっても我らは生きていかねばならぬということだ。
you know,
dum vivimus vivamus、
生きている間は、生きようではないか。
(古代ローマのことわざ。
ヤマザキマリ・ラテン語さん『座右のラテン語』SB新書2025年 p.150。一部改変)
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年1月31日より加筆修正)
「年賀状じまい」と弱い紐帯。

FIND/47より鹿児島 霧島神宮
2024年末から2025年年始にかけて、「年賀状じまい」という言葉をずいぶん聞いた。
毎年年賀状を出していたが、今年を限りにおしまいとさせていただく、みたいな意味だと思う。
昔と比べて年末ぎりぎりまで仕事もあるし、メールやSNSでふだんからなんとなくつながりもあるし、郵便代も上がったし、という複合的な理由だろう。
非常によくわかる。
年末だけ郵便需要が爆増してバイトの配達員なども大量に差配しなければいけないし、郵便局側としても「年賀状じまい」は消極的に賛成なのだと思う。年賀ハガキ売っておしまいならいいんだろうけど、配達しないといけないからバイトや残業代とか考えると利益という面では限られているはずだ。
「年賀状じまい」したら年末ラクだろうなとは思う。だが当面、規模を縮小しながらも続けようと思っている。
なぜか。
儀礼とか伝統とかお気持ちとか、そうした不可算なものは除外し、あえて功利主義的に考える。
儀礼とか伝統とかお気持ちみたいなことを論じるとどうとでもいえるし、どこかで「失礼クリエイター」ことマナー講師に聞きつけられて寄ってこられてもいけない。
あえて功利主義的に考えたとき、年賀状は「弱い紐帯」を維持するのに非常に有効な手段である。
生きていくために大切なのは、誰か1人との深くて強い一本の絆(だけ)ではなく、多くの人との浅くて弱い無数の絆である、というのが「弱い紐帯」の考えかただ。
困ったときのちょっとした手助けが、ぼくらを破滅から救ってくれるのだ。
この「弱い紐帯」仮説は、アメリカの社会学者グラノヴェターの研究などにより示された(M.グラノヴェター『転職 ネットワークとキャリアの研究』ミネルヴァ書房 1998年)。
転職が盛んなアメリカで、人々はどのようにして新しい職を見つけているか、グラノヴェターは居住者9万8000人(当時)のマサチューセッツ州ニュートン市をサンプルとして調べたのだ。
人々は転職するときにどうやって新しい職を探しているのか。求職者に新しい職を紹介するのは誰かをグラノヴェターは調べた。
アメリカは転職大国とはいえ、転職は人生の一大事だ。
そんな一大事を左右するのだから、新しい職を紹介してくれるのは家族や親友など「濃い」関係の人ではないかと考えるのが普通だ。
だが意外にも、転職者に新しい職の情報をもたらしたのは仕事上の友人や知人、恩師などが多かったという(前掲書 2章)。
興味深いのは考察で、家族や親友などの「濃い」関係の人(「濃い」「薄い」について、グラノヴェターは週に何回会うかを指標にしている)は、求職者と行動範囲がかなり重複するため、求職者が知らない情報が入ってきにくいからではないかと述べられている。ここらへんはネット時代以前の調査であることに留意。
同じ「界隈」の人とは「濃い」関係性が築きやすいが、同じ「界隈」だとは入ってくる情報はカブる、ということだろう。
そういうわけで、グラノヴェターの調査においては、求職者は「薄い」関係性の知人友人から新しい職を紹介してもらう割合が多かった。
いろんな行動範囲の人と薄くつながっていると新しい情報が入ってきやすい、ということだろう。
このグラノヴェター『転職』が、「弱い紐帯」仮説の論拠の一つとなっている(はず。誤読してたら教えて下さいませ)。
「弱い紐帯」は、ときどき手入れをしてキープしないといけない。放置していれば切れてしまうのだ。
というわけで、「弱い紐帯」が僕らを破滅から救ってくれる蜘蛛の糸で、そうした「弱い紐帯」を年に一回のご挨拶である程度キープできるかもしれないから、当面年賀状は続けようかなと思う次第であります。
今年もよろしくお願いします。
(『カエル先生・髙橋宏和ブログ』2025年1月15日を加筆・修正)
Pieces of a dream。
「それって、夢は何かってことですよね?」
K先生が言った。
「…セスナの免許取るってどうですか?」
会話や対話は楽しい。自分では絶対に出てこない発想がポンポン飛び出してくる。
「予定外に急に、2、3時間ヒマな時間ができたら何してます?」
ここのところ会う人ごとに、そんな質問をしている。
実際に自分がそんな目、すなわち突然2、3時間ヒマになって「さてどうしたものか」と困った経験があるからだ。
ちなみに、酒を飲むのは無しとする。
以前なら2、3時間ヒマになっても、ふらりと本屋に行ったりCD屋に行ったりした。
本屋に行くのは今も楽しいが、一方で、「この本のネタもとはたぶん古典のアレだよな。新しい本買うのもいいけど、ネタもとの古典はまだ読まずに積んであるし、読むべき古典はいっぱいあるな」という時期に入ってしまっている。
CD屋も、そうとうの店舗が街から消えてしまった。
若い時は街をぶらぶらするだけで楽しかったが、今は感性が摩耗してしまった。
酒を飲まないという“縛り”が無ければまた話は変わってくるだろうが。
急に2、3時間ヒマになったら何をします?という質問に対する答えは人それぞれだった。
「ヒマになったらジムに行ってる」
「料理。それか本屋に行ってレシピ本探してる」
「ひたすら散歩」
「葉巻バーで葉巻吸う」
「調べて映画見に行く。学生時代、映研だった」
「時間が空いた時に行くと決めている喫茶店がある。とにかく時間が空いたらそこに行って本読んだり」
「ヨガかな」
面白かったのは、
「歌を習おうと思ってる。別に誰に聞かせるわけじゃなくて、自分が歌うまかったら楽しくない?」
なるほど。
「ドローンとかどう?楽しいよ」
と言ってくれた先輩もいた。
「空からの視点なんて普通ないじゃない?前にドローン買って飛ばしたら楽しかった」
そんな中で出てきたのが冒頭のK先生の話だった。
余暇や空き時間を、“夢”実現のひとかけらととらえる発想は自分には無かったので面白かった。
たしかに「空を飛んでみたい」というのは人類の夢だ。
自分の実生活で空を飛ぶなんて無いことだし、セスナの免許を取るプロセスや、その気になればセスナ飛ばせるという感覚そのもの楽しそうだ。
そんなことを想像するだけで楽しくなってきた。
善は急げで、まずはセスナ買ってくる。

photoACより
(『カエル先生・髙橋宏和ブログ』2024年11月6日より加筆修正)
ポテトな驚天動地。
「え“え“え“!」
度肝を抜かれる、天地がひっくりかえるというのはこういうことを言うのだろう。何歳になっても死ぬほど驚くことはある。いまだにショックから立ち直れない。
ウズベク料理をつつきながらTさんから教えていただいた秘密で、世界の見方が激変した。

「アメリカ行くとね、どでかいステーキの横に、山盛りのフライドポテト出てくるでしょう。
あれ見てボクらは“さすがアメリカ人はよく食べるなー”とか思うけど、なんとね、あのフライドポテト、食べなくてもいいみたいなんです。
もちろん食べる人もいるけど、ちょこっとだけの人も多いし、全然食べない人もいる。日本の、“サシミのツマ”みたいなもんですね。
食べてもいいし食べなくてもいいみたいです、アメリカのフライドポテト」
え“え“え“!
「食べないのになんであんなに山盛りかって?
理由はね、“山盛りのほうが嬉しいから”。
映画館のバケツみたいなポップコーンも一緒。全部食べない。
全部食べないのに山盛りの理由?それはね、“そのほうが嬉しいから”」
え“え“え“!
実はいまだにショックから立ち直れない。
アメリカも広いし州によって“別の国”くらい違うから、在米のかた、実際のところどうでしょうか?
おまけ)1か月間マクドナルドのメニューだけ食べ続ける映画『スーパーサイズミー』に、数十年ビッグマック(でしたっけ?)を食べ続けてる人が出てきて、でもその人は太ってなくてしゅっとしてるんですね。
その秘訣を聞いたら「ビッグマックは食べるがフライドポテトは食べない」って言ってた記憶。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2024年10月26日を加筆修正)
『病院が地域をデザインする』出版記念 梶原崇弘氏 紙上インタビュー
2024年6月に『「究極の地域医療」を目指す中小病院の挑戦 病院が地域をデザインする』が出版されました。
著者の医療法人弘仁会理事長の梶原崇弘さん(麻布H4年卒)にインタビューしてきました。
編集部:『病院が地域をデザインする』、ご出版おめでとうございます!読者のかたに向けて、自己紹介をお願いします。
梶原(敬称略)
H4年卒の梶原です。自由には責任がともなうものですが、高校在学中はまだまだ未熟で、麻布の自由の部分だけを満喫してしまいました。今も折に触れ助けてくれる多くの友人に恵まれたことが一番の財産だと思います。
編集部:今回出版された『病院が地域をデザインする』に込めた思いとは。
梶原:超高齢化社会・少産多死社会を迎えるなかで、「その人がその人らしくその人の希望する場所で最期を過ごす」ためには「地域包括ケア」の視点で医療・介護・福祉が連携した社会の構築が求められます。しかし、都市部と過疎部など地域ごと異なった背景のもとに画一的な制度を当てはめようとしてもうまくいきません。我々の取り組みは多くの取材をいただきますが、背景や思いを知っていただき活動のヒントになればという思いで今回の出版に至りました。
編集部:ご著書の中で、「地域に屋根のない総合病院をつくる」とお書きになっています。「屋根のない総合病院」とは、どういったものでしょうか。
梶原:医療の高度専門化・細分化に伴い、一つの病院ですべての地域ニーズに応えるのには限界があります。地域の開業医の先生方と「顔が見える」を超えた、「人柄や能力のわかる」関係を構築することで地域の名医とともに総体として住民を守る総合病院のような役割を担うことを目指しています。
編集部:ご著書では、ご自身の病院のシステムエンジニアを地域のクリニックへ派遣しているエピソードが書かれています。どのような理由でシステムエンジニアの派遣を始められたのでしょうか。
梶原:今回インタビューいただいている、同級生の高橋先生と外来で話をしているときに、「クリニックのシステム修理を毎月頼んでいるけど、お金はかかるけど一向に希望にあった改善が進まない。」という相談をうけました。医療分野のICTコストは費用全体の5%くらいを占めるにもかかわらず、医療の特殊性を理解したSEとマッチングすることは難しく、かつ継ぎ足しで構築されたクリニックなどは秘伝のたれのようなシステムになっていて再構築が困難であるという実態を知りました。治らない修理を繰り返してカモにされているクリニックも多そうだと思ったので、当法人に所属する医療の特殊性を理解しているSEを派遣して、安心できるシステム作りに役立てていただこうと思ってこの企画を始めました。
編集部:『病院が地域をデザインする』の中では、板倉病院を「都市型地域密着病院」と位置付けておられます。都市型地域密着病院をマネージメントするお立場から、日本の医療の未来をどうみていらっしゃいますか。
梶原:先述したように、超高齢化社会を迎え医療・介護ニーズはますます高まります。いわゆる団塊の世代がどのように穏やかに終焉を迎えるかが当面の課題になるわけです。
しかし、公定価格で診療を行う医療業界では給与の引き上げも簡単にはできないため、他業種との人材の取り合いで不利になります。そのため、看護・介護人材だけでなく、事務職の人材確保なども非常に困難な状況です。タスクシフト・タスクシェアをしたくてもシフトする人材がいないという未来が現実化しています。ICT活用によるDX推進により業務効率や生産性をあげて地域全体で臨む医療機関だけが生き残れる厳しい環境といえます。
我々は地域の医療機関の役割分担を明確にして、住民の交通整理を行うことで医療アクセスの適正化をはかり、質を担保しつつ安心な医療提供が維持できると思っています。
編集部:ご著書では「地域が病院をつくり、病院が地域をつくる」と、地域も一つの大きなテーマになっています。梶原さんは、日本の地域の未来をどうみていらっしゃいますか。
梶原:都市部においては、いわゆる地域コミュニティは希薄化しており、コミュニティによる高齢者の見守りや気付きを得ることは難しくなっています。しかし、民度の低下は否めないものの、当院で行っている「こども食堂」には多くのボランティアが参加してくれているように、個人の単位では思いのある方がまだいると思います。場がなくて行動できていない人も多い印象なので、病院を一つのハブとして地域コミュニティを盛り上げ、人と人とのつながりをサポートしていけば、地域の未来は充実したものになるのではないかと思っています。
編集部:最後に『麻布流儀』の読者へのメッセージをお願いします。
梶原:病院という既存の概念を超えて、地域医療をデザインするという取り組みを始められた一因に、麻布中高の自分で考え、判断する習慣があったかもしれません。もしご興味がありましたら、一緒に地域医療を盛り上げていきましょう。いつでも遊びにきてください。
編集部:ありがとうございました!
梶原崇弘氏プロフィール(写真左)
1973年千葉県船橋市に生まれる。麻布高等学校卒業後、日本大学医学部医学科入学。 医学部卒業後は肝胆膵・消化器外科医として、高次医療機関にてがん領域を専門に研鑽を行っていた。がん研究センター中央病院肝胆膵外科、日本大学附属板橋病院消化器外科副 医局長を経て、2011年、実家である板倉病院院長就任をきっかけに、地域密着中小病院の 在り方や実現可能な地域包括ケアシステムの構築に軸を移し、安心して過ごせる地域医療を目指している。
聞き手:高橋宏和(写真右)
1973年千葉県生まれ。麻布高等学校卒業後、千葉大学医学部入学。脳神経内科として千葉県内外で勤務。2017年千葉県船橋市にある中條医院を継承し理事長就任。
2024年11月5日はスーパーチューズデー-なぜアメリカでは火曜日に大統領選挙をやるのか

photoACより
2024年11月5日、アメリカで大統領選挙が行われる。
細かく言うと、行われるのは大統領を選ぶ人、選挙人を選ぶ選挙だ。
全米で538人の選挙人を選び、選ばれた選挙人たちが大統領を選ぶ。それぞれの州の選挙人数は、各州の上院と下院の議員数の合計と等しい。
選挙人を選ぶ選挙は、11月第1月曜日の翌日、火曜日と決まっている。
(参考サイト NHK『アメリカの大統領選はどう進むの?』)
https://www3.nhk.or.jp/news/special/international_news_navi/us-election/flow/
このように、アメリカでは大きな選挙は火曜日にやることが多い。
その理由をご存じだろうか。
答えは、「国土が広く、移動に時間がかかるから」。
その昔、馬や幌馬車でアメリカ人が移動していたころ、広大なアメリカ全土から投票所に行くのには大変時間がかかった。
ワイオミングの山奥やノースダコタの大農場から出発したら、下手したら投票所につくまで丸1日かかる。週のはじめの月曜日に家を出ても投票所に着くのは翌日の火曜日だ。
だから、アメリカでは大きな選挙は火曜日にやる。
日曜日に家を出ればいい?バカなことを言ってはいけない、日曜日は神のおつくりになった安息日ではないか。余計なことをせず、家でじっとしていなければいけない。
この話をはじめて知ったのは、東大からプロ野球に入った小林至の本『アメリカ人はバカなのか』(幻冬舎文庫 平成15年 p.96-97)だった。
俗説かと思って調べたら、アメリカには『Why Tuesday?』というNPOまであって、選挙日を火曜日から週末に変えましょうという啓発活動をしている。
(参考サイト『Why Tuesday?』FAQ)
https://whytuesday.org/faq
TEDでやった代表のプレゼンはわかりやすく、一見の価値がある。その中で上記NPOはギングリッチやジョン・ケリーといったいろんな政治家に「どうして選挙を火曜日にやるんですか?」とインタビューしているが、誰も答えられない(答えられない政治家ばかり出している可能性はある)。
NPO団体、Why Tuesdayによれば、火曜日に選挙をやるなんてことは独立宣言にも合衆国憲法にも書かれていない。1845年の「バカげた法律」に書かれている。
彼らはこれを変えて、選挙は火曜日ではなくて週末にやるように訴えている。
何故か?
前掲書の中で小林至はこう書いている。
<(略)今でも火曜に固執している理由は、伝統に名を借りて庶民を排除しているだけだ(略)>(p.96)
多くの勤め人たちの会社は火曜日は休みではない。仕事中に抜け出して投票に行けるほど暇な職場は少ない。そうなると、火曜日に投票に行けるのは大農場主や自営業者、熱心な政治支援者や宗教右派、リタイアした人や学生、失業者が中心になる。
「フツーの勤め人」は現実問題として投票に行けない/行かない。だから政治家の政策も投票に来てくれる人が喜ぶもの中心になりがちで、「フツーの勤め人」は後回しになるのではないかという指摘だ。
2012年の「Why Tuesday?」のインタビューでも、代表のJacob Soboroffは「15の州(*インタビュー当時)では事前投票ができず、火曜日しか投票できない。シングル・マザーやシングル・ファーザー、2つ3つ仕事を掛け持ちしている人はどうなる?」と問題提起している。
https://www.youtube.com/user/WhyTuesday
フツーの勤め人が火曜日に、どれくらい大統領選挙に行くものなのかアメリカに住んだことがないのでリアルな感触はわからない。「フツーの勤め人」がどれくらい投票に行くものなのか、身近にアメリカ人がいるかたは聞いてみて教えてください。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2016年11月7日を加筆修正)