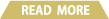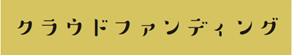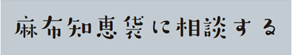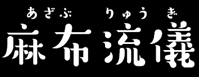フランス人D君の教えてくれた日本人、ヨーロッパ人、アメリカ人の違い-HowとWhyとHow much仮説(後編)
 (写真:photo ACより)
(写真:photo ACより)
知人のフランス人D君があるときこんなことを言った。「なにかをやるとき、ヨーロッパ人がこだわるのはwhyだが、日本人はhowにこだわる。そしてアメリカ人が最もこだわるのがhow muchだ」。
たいへん面白い指摘で、このことについてずっと考えている。
アメリカ人のこだわるHow muchは、摩天楼や、ビル・ゲイツやザッカーバーグ、持てる1%と持たざる99%に行きつく。
ヨーロッパ人のWhyは、明証、分析、総合、枚挙の四原則によって<ワレ惟(おも)ウ、故ニワレ在リ>(デカルト『方法序説』 岩波文庫 p.46)に至り、同時に、不完全な自分なのに完全性が分かるのは、完全な者がその概念を与えたはずだ、だから完全なる者=神が存在するのだ(同書 p.49)、というところに辿りつく。
それでは、我らがhow、「どのように」はどこへ到達するのだろう。
言い換えると、「どのように」の集積である「道」はどこへ向かうのだろうか。
一つの答えは、どこへも辿りつかない、というものだ。
すなわち、「どのように」=「道」の永遠の追求自体が目的地であり、なんらかの定常状態にはいつまで経っても落ち着かないのかもしれない。それはあたかも永遠に0に近づき続ける漸近線の如く、理想形や完全体に永遠に近づき続けるが達しないムーブメントだ。究極の真・善・美を求め続ける旅そのものが、日本の求道者の願いなのかもしれない。
俳句の道を求め続けた芭蕉の生涯最後の句は、「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」だった。
「道」はどこにたどりつくかのもう一つの答えは、「無」だ。
中島敦の短編、『名人伝』は弓の道を究めた男、紀昌(きしょう)の話である。
紀昌は名人、飛影(ひえい)に弟子入りし、何年もの修行の末に百発百中の名人となる。速射をすれば的中した矢の後ろに次の矢が刺さり、落ちる間もなくその次の矢が刺さる。次々と速射して百本の矢がまるで一本の矢のように連なり、的と弓を一直線につなぐほどの腕前となる。
もはや師、飛影も恐るるに足らずと思った紀昌は、さらにすごい老師がいると聞き、西へ旅立った。
山奥で、百歳を超えるよぼよぼの老師は言う。お前のはしょせん射之射(しゃのしゃ)だ、大事なのは不射之射(ふしゃのしゃ)だ。
そういって老師はなにも持っていない手に見えない弓を持ち見えない矢をつがえ、空高く飛ぶ鳥を射落とした。
弓の道を究めた老師には、もはや弓も矢も要らないのだ。
話はそれで終わらない。
老師のもとで9年間修行し山を降りたとき、紀昌はすっかり変わってしまっていた。
<以前の負けず嫌いな精悍な面魂は何処かに影をひそめ、何の表情も無い、木偶の如く愚者の如き容貌に変わっている>(中島敦 『李陵・山月記』 新潮文庫 p.30)のだ。それだけではなく、並ぶもののない名人になったはずの紀昌は、いつまで経っても弓を射ろうとしない。
それどころか、友人の家に置いてある弓と矢を見て、心底不思議そうに聞く。「これはなにをする道具だ」、と。とうとう死ぬまで紀昌は弓を射ることはなかった。
弓の道を究めに究めたその先が、弓も矢も忘れ去り、ただただ無為。
面白いことに、『名人伝』のモチーフの中国の古典の列子の湯問編、少なくとも手持ちの本では、山奥の老師の不射之射の話も、弓道を究めつくした紀昌が弓も矢も忘れ去る話は出てこない。たんに紀昌が師の飛衛を殺そうとするが互角で叶わず、互いを認め合って親子の契りを交わす話だ(列子では飛「影」ではなく、飛「衛」表記。『中国の古典⑥ 老子・列子』徳間書店 p.237-8)。
『名人伝』の後半部が中島敦のまったくのオリジナルなのか、ほかの古典に似た話があるのかはわからないが、「道」を究めつくした先が「道」そのものを忘れ去り、「道」の先には「無」がある、という感覚は、なんとはなしに日本人にはしっくりくる。
似た例として、会田雄次は、大山巌元帥や、西郷隆盛の話を挙げている。
誰よりも砲術の「道」を究めた大山巌元帥が激戦中に、「大砲ってのは、上に向くほど遠くに行くのかな」と部下に尋ねた、という(会田雄次 『日本人の意識構造』 講談社現代新書 p.70-72)。
また、西郷隆盛と言えば上野の銅像の朴訥としたイメージだが、よくよく考えると実は彼は明治のスーパーエリートだ。
<その彼の全努力が、ぼけることに傾注され、あの茫洋たる大南洲翁が出現したとき、国民の敬慕が集中したのだ>(同書 p.88)。
ここでも、「道」を追求しつくした先には「道」すら忘れて「無」となるのがよい、という日本人のある種のフィーリングを感じることが出来る。
How=「道」を究めた先にはただ「無」がある。それはけっして消極的な「無」ではないのだろう。
「道」は長く曲がりくねっているが、「道」を究めきって関所を越えたときには、東西南北に活路が開け、なににも捕らわれることのない自由自在、天衣無縫の積極的な「無」があるのではないか。「道」の一つ、茶道では、所作の一つ一つがこと細かに決まっているが、茶道の祖、利休は「茶の湯とは ただ湯をわかし 茶をたてて のむばかりなる 事と知るべし」という言葉を残している(千宗室・千玄室 監修 『裏千家茶道』 今日庵発行 p.40)。
仮説に基づき、今度はアメリカ人について考える。アメリカ人がhow muchにこだわるようになった理由は、比較的想像しやすい。
旧大陸から渡ってきた開拓者たちにとって、細かい理屈はどうでもよかった。荒地を耕し農作物を育て、とにかく目の前の課題を解決していくしかなかった開拓者たちにとっては、理由もプロセスもいらない、結果がすべてだった。どんな手を使ってでも結果を出し続けなければ、フロンティアでは生きていけなかったはずだ。
また、アメリカは「人種のサラダボウル」と言われる多民族国家だ。文化的ルーツの異なるエスニックグループ同士、それぞれ行動の理由や様式は違い、その違いを埋めるには途方もない労力が必要だろう。
しかし、理由やプロセスは千差万別であっても、結果は誰の目にも見えやすい。各エスニックグループ間の調整をするときに、共通のものさしとしていちばん使いやすかったのが結果=how muchの価値観だったのではないだろうか。
アメリカ的な考え方を一言で表す言葉は「プラグマティック」だ。
<プラグマティックな方法なるものは、(略)定位の態度であるに過ぎない。すなわち、最初のもの、原理、「範疇」、仮想的必然性から顔をそむけて、最後のもの、結実、帰結、事実に向おうとする態度なのである。>(W.ジェイムズ『プラグマティズム』岩波文庫 1957年 p.46)
原理や規範がそれぞれ違う多民族国家をうまく運営するには、万人が見て納得する結果を共通の価値観とするのが手っ取り早かったのであろう。
さて、それではヨーロッパ人がwhyにこだわるようになったのは如何なる理由があったのか、想像の翼を広げたい。
和辻哲郎は、人間の行動様式に影響を与えるものとして「風土」に着目した(和辻哲郎『風土―人間学的考察』 岩波文庫 kindle版)。和辻は、ヨーロッパの風土の特徴を、「牧場」と呼ぶ(上掲書1178/4865)。ヨーロッパの風土は、湿潤と乾燥との総合だと指摘する。ヨーロッパの風土では、夏は乾燥期であり、冬は雨期だ(と和辻は述べている)。
乾燥した夏は、日本のような雑草をもたらさない。<しかるにヨーロッパにおいては、ちょうどこの雑草との戦いが不必要なのである。土地は一度開墾せられればいつまでも従順な土地として人間に従っている。隙を見て自ら荒蕪地に転化するということがない。だから農業労働には自然との戦いという契機が欠けている>(上掲書1356/4865)
ヨーロッパでは一度耕した土地は荒れ果てることなく、耕されたままである。かつてスペインの海沿いを鉄道で旅したことがあったが、車窓から見られる植生の単調さに驚いた。どこまで行っても見えるのはアーモンドかオリーブの木のみ。
(和辻の説によれば)ヨーロッパでは自然は単純で従順だ。そうした単純な気候風土では因果関係が見えやすい。
<すなわち自然が暴威を振るわないところでは自然は合理的な姿に己れを現わして来る。
(略)人は自然の中から容易に規則を見いだすことができる。そうしてこの規則に従って自然に臨むと、自然はますます従順になる。このことが人間をしてさらに自然の中に規則を探求せしめるのである。かく見ればヨーロッパの自然科学がまさしく牧場的風土の産物であることも容易に理解せられるであろう。>(上掲書 1435/4865)
こうしてヨーロッパの単調で従順な風土から合理主義が生まれ、因果関係、特に因=whyにこだわる文化が生まれたのではないか。
ヨーロッパの風土が「牧場」だとすると、日本の風土は「モンスーン的」であると和辻は述べる。そしてモンスーン的風土は、人間を受容的・忍従的にする。さらに日本人の性格に影響を与えたのは台風の存在だ。
台風の特徴は、突発的で猛烈であるということだ。21世紀の今でさえ台風の発生と進路を予想するのは難しく、どんなに人間ががんばっても台風の被害は出る。なぜ=why台風が起こるかなどと考えても無益だし、台風に抗っても結果は常に人間の負けだ。考えて意味があるのはただ、台風という突発的猛威のなかどのように=how身を処するかだけだ。
昔から、「地震・雷・火事・親父」という。地震も雷も火事も親父の怒りもすべて、突発的に起こる。起こってしまう理由を考えても仕方がないし、起こったときにどう対処するかを追求するしかない事態ばかりだ。そんな風土の中、日本人はwhyでもなくhow muchでもなく、howにこだわるようになっていったのではないだろうか。
昔フランス人D君が言った「ヨーロッパ人はなぜ=why、アメリカ人はなんぼ=how much、日本人はどのように=howにこだわる」というテーマについてここまで考えてきた。
考えれば考えるほど興味深いテーマだ。
これからもこのテーマについて考え続け、手作り感覚のできるだけ丁寧なやり方でまじめにがんばってこのテーマにこだわっていきたいと思う。
そもそもなぜ、そんなにこだわるのかって?そんなことは知らない。なぜなんてことは、ヨーロッパ人に聞いていただきたい。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』http://www.hirokatz.jp 2016年5月10,13日より加筆・転載。)