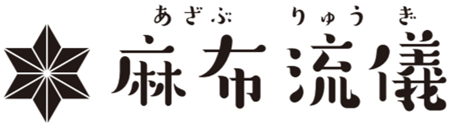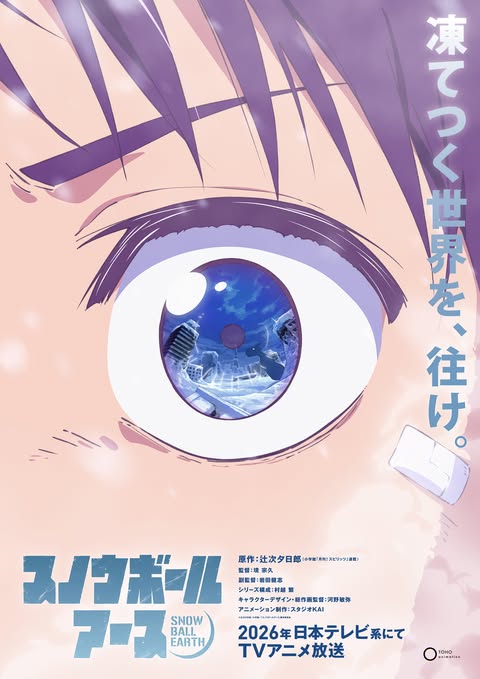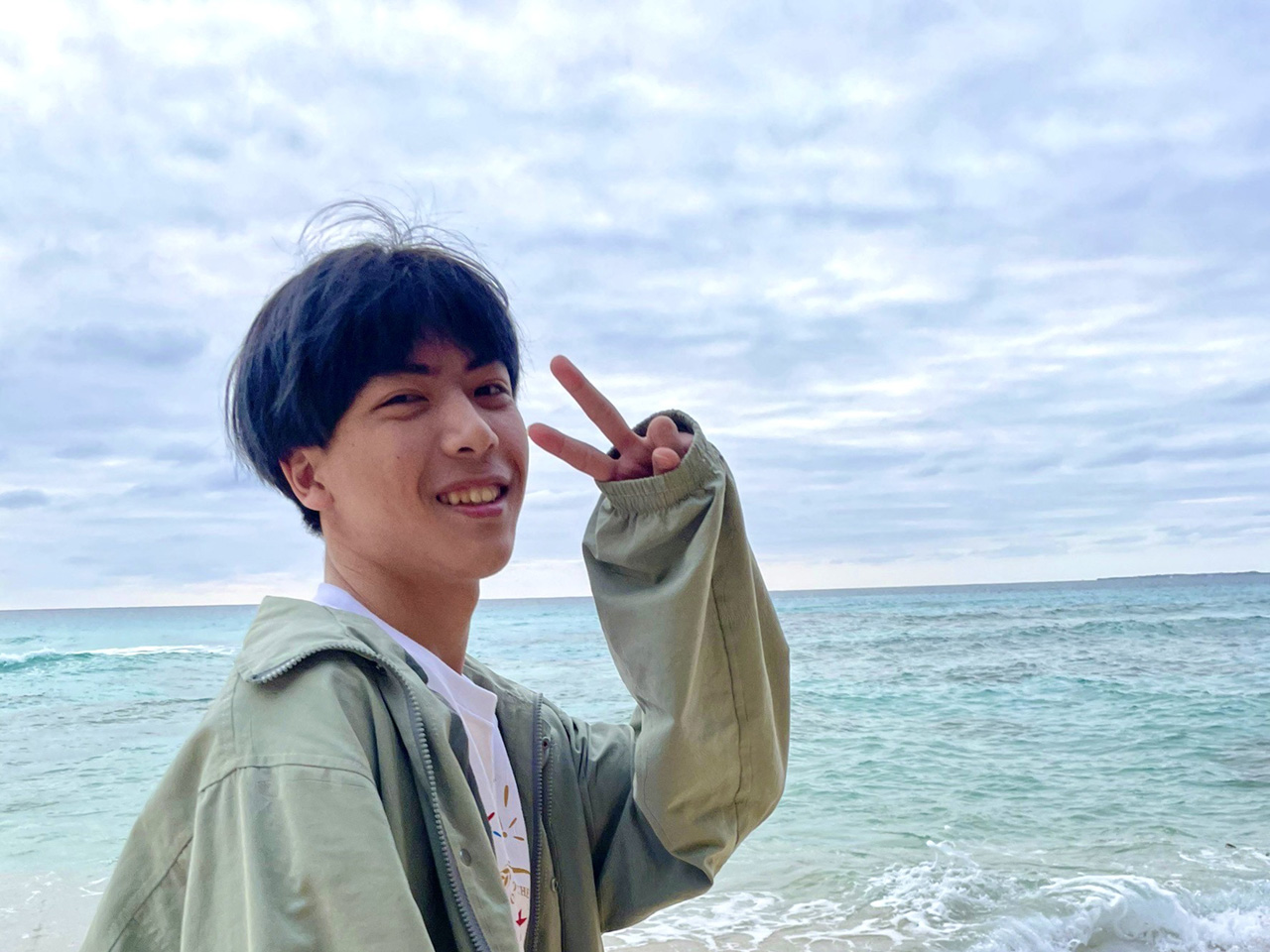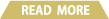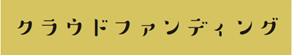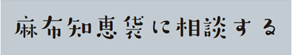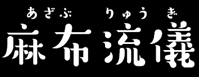いわゆる”脳科学”を批判する。2
いわゆる“脳科学”、「最新の脳科学によれば人間とはこうだ」みたいなエセ科学のブームについて嫌悪感と警戒感を抱いている。嫌悪感と警戒感の理由については前述の通り。
さて、いわゆる“脳科学”の多くは、ごく限られた条件下の限定的な科学的発見を、恣意的につまみ食いし自分の思いつきや経験論に宣言なく無理やり当てはめ、仮説ではなく「ご宣託」として押し付けてくるものである。
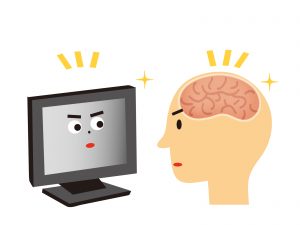
イラストACより
では、そんな胡散臭いものがこれだけ長きに渡ってブームになっているのはなぜか。言葉を変えれば、人々はなぜいわゆる“脳科学”に心惹かれるのか。
複雑怪奇、不可解で理不尽な人間という存在や、社会というものを単純明快な「最新の脳科学」とやらでわかったものにしたいという欲求はあるだろう。わからないものをわからないまま付き合っていくのは知的スタミナを要する。それよりは「最新の脳科学」によればこうだよね、としたり顔できたほうが楽だ。
精神科医の斎藤環氏は別の見方を提示している。
“脳科学”が多くの日本人に受けるのは、〈脳が様々な問題を外在化する装置になっている〉からではないかという仮説だ。
斎藤氏は佐藤優氏との対談でこう述べる。
〈斎藤 自らにとって不都合な事象を認識した時に、それを心で受け止めようとすると、自分の内なる問題、自己責任になってしまうこともあるでしょう。しかし、脳のせいにすれば、それはまあ生まれつきなのだから自分の問題ではないんだ、ということにできる。そういう不思議な思考回路ができている感じがするのです。
佐藤 自分がこんな人間なのは、自分をコントロールする脳内分泌物のせいだ。もっと言えば、そういう脳のつくりを遺伝させた親のせいだ。だから自分に責任はない、恨むべきなのは親なのだー。〉
(〈〉内は佐藤優・斎藤環『なぜ人に会うのはつらいのか』中公新書ラクレ2022年 p.78-79)
なんでもかんでも自己責任を押し付けられる現代社会において、“脳科学”は「あなたのせいじゃないよ、ぜんぶ“脳”のせいだよ」と甘く囁く。
“脳科学”は「問題の外在化」をすることにより現代人を自己責任から解き放つ。だから“脳科学”はブームになるのではないか、というのが上掲書・上掲箇所における斎藤環氏の考えである。
“脳科学”の本質が「問題の外在化」であるとすれば、全く別の側面がある。
斎藤環仮説が正しいとすると、知的良心を捨てることができれば『人のせいにする脳』という本を書いたり、あるいは「問題の外在化」にあらがうような『NOと言える脳』という本を書いたりできるかもしれない。
”脳科学”ブームがいつはじまったのか。ふりかえってみると、総胆管末端筋の研究で学位を取ったという春山茂雄氏の『脳内革命』(1995年)あたりだろうか。以来ずっと”脳科学”ブームである。
なぜ“脳科学”がそれほどまでにウケるのか。
斎藤環氏は、“脳科学”は問題を「外在化」し、自己責任論から読者を解放してくれるからウケるのではないかと指摘した(前述)。
あなたが抱えている問題はあなたのせいじゃない、脳のせいだ。脳のホルモンが前頭葉がシナプスがこれこれこうだから問題は起こるのだ。あなたのせいじゃないあなたのせいじゃない脳のせいだ脳のせいだあなたは悪くないよと“脳科学”は甘く囁く。だから“脳科学”は人々の心をとらえるのだというのが斎藤環仮説だと思う。
この仮説を考えていて面白いことを発見した。
“脳科学”が問題を「外在化」し、問題は自分の「外部」にあると示すというのがここでの斎藤環仮説の本丸だと思う。
だが面白いことに、多くの読者が「外在化」された問題を「仕方ない」と思うのと対照的に、一部の読者は問題が「外」にあるからこそコントロール可能と思うのではないか。
たとえばイーロン・マスクのような人物は、問題が「外」にあればあるほどコントロール可能と考える(のではないか)。
彼のような人物は、我がことよりも「外部の問題」こそコントロール可能、解決・克服可能と考えて燃える。
そんな人たちにとっても、“脳科学”が問題を「外在化」させることで「“脳”をハックしてうまいことやろう」と意欲をかきたてられる。
すなわち、“脳科学”が問題を「外在化」させることで、「外部」の問題はコントロール不可能と思う多くの人たちも、「外部」の問題こそコントロール可能と思う少数の人たちも真逆のアプローチで“脳科学”を受け入れる。そんな構造があるのではないか。
“脳科学”は、前者には癒しと慰めを、後者には励ましとやる気を与えてくれるのだろう。
まあここらへんになってくると「理屈とポストイットはどこへでもくっつく」というヤツで、どうとでも言えるのだが、「“脳”をハックしてやろう」という見方で“脳科学”をとらえる一群がいるというのは悪くない見方だと思う。
いずれにせよ、誰かが言っていることを無批判に受け入れ信じ込むというのは科学ではない。
眼の前の事象や誰かが唱えている仮説を懐疑的・批判的に検証して、検証に耐えるものだけを「ひとまずの真実」として受け入れるのが科学なので、”脳科学”とは科学的につきあっていくべきだろう。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年3月11日、3月12日を修正加筆)