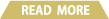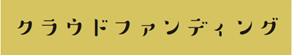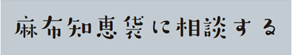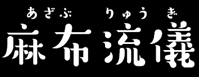「医者は死というものをどうとらえているか」という問いと、ひとまずの答え。
 (写真:photo ACより)
(写真:photo ACより)
医者になって今年で20年になる。
医者の仕事をしていると、「医者は死というものをどうとらえているのか。なんでもかんでも生かせばよいという考えが医者にはあるのではないか。医者が正しい死生観を持つことが、不要な医療を無くすことになるのでは?」という意見を聞くことがある。これについて現時点で考えていることをまとめておきたい。
「医者は死をどうとらえているか」ということに対する答えとして、数年前までぼくは論語の「未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんや」(先進篇)を愛用していた。
孔子の弟子の子路が孔子に聞いた。「先生、死ってなんですか?」
それに対して孔子がこう答えたわけだ。「私は未熟者で、まだ生きるということすらわからない。それなのになぜ死ということがわかるだろうか」
人類最高の知性の一人孔子ですら死をわからないのに、ぼく如きが分かりません、というふうに言っているのである。
上記はややはぐらかしであるが、一言で死と言っても持つ意味は様々だ。
一人称の死、二人称の死、三人称の死。
例えば「死体」と「遺体」の違いは何か。
波平恵美子『日本人の死のかたち』(朝日新聞社 2004年)によれば、どこの誰かわからない死んだ身体は「死体」と呼ばれる。しかしその死体がどこの誰か判明していくと、それは「死体」ではなく「遺体」となる。そこに人格が存在する(した)のか、周囲との関係性があるのかが「死体」と「遺体」の差なのだ(同書p.80-82)。
ロックバンドTHE YELLOW MONKEYの曲「JAM」にこんな歌詞がある。
<外国で飛行機が堕ちました ニュースキャスターは嬉しそうに
「乗客に日本人はいませんでした」「いませんでした」「いませんでした」
ぼくは何を思えばいいんだろう>
死についてのニュースなのに、この歌のニュースキャスターが嬉しそうに「乗客に日本人はいませんでした」と言えるのは、おそらく視聴者と関係性がある被害者がいない可能性が高いからだ(グローバル化で国境を越えた知人友人が増えた現代では成り立たない歌詞かもしれない)。
死をどうとらえるかと言うけれど、関係性によって全然変わってきてしまうわけである。
また、時に、死が救いになることがあるのかもしれない、ということぐらいはぼくにも分かる。
死よりも過酷な生もあり得る。
ドルトン・トランボの小説『ジョニーは戦場へ行った』(角川文庫 昭和46年)の主人公ジョニーはコロラド育ちで、異国の戦場で砲弾にあたった。
ジョニーは目を失った。
ジョニーは鼻を失った。
ジョニーは口を、耳を、失った。
右腕も、左腕も、右脚も、左脚も、失った。
暗闇の中、無音の中でジョニーは生きる。病院のベッドの上で身動きもできず、言葉を発することもできぬまま。
事実は小説よりさらに過酷で、もっと残酷な生は世にあふれているのだろう。
だがしかし、ぼくは医師が彼個人の死生観をふりかざすことを好まない。
死生観を持つことは自由だし、ぜひそれぞれの死生観を深めるべきだと思う。
しかし、社会において、病院や医師はあくまでも可能な限り命を救うことを要求されているとぼくは思う。可能な限り命を救うことは病院や医師の社会的役割である。
警察の社会的役割が悪者を捕まえる事であるのと同じことだ。
一警察官が「アウトローの人って必要悪だよな」と考えていたとしても、その個人の思いを業務に反映されたら困る。「必要悪だから逃がしますよ」とか言われたら困ってしまうのだ。
それと同じように、「ただ長生きすればいいってもんじゃない」と考える医者がいても、それを業務に反映されたら困るのだ。だって、自分の主治医がどんな死生観を持つ医者かなんてわからないし、それぞれの死生観に忠実に仕事をされたら、「長生き最高!!」と思う医者の場合にはめいっぱい治療を受けられて「長生きしてもつらいだけ」と思う医者にかかったらそこそこで治療を打ち切られてしまうことになるのだ。そんなロシアンルーレット、やだ。
死生観とどこまでどんな治療をすべきかを決めるのは一医療技術者である医者ではなく、あくまでも社会だ、と思うわけであります。
というわけで、冒頭の「医者は死というものをどうとらえているのか」に対し、最近は徒然草から「人、死を憎まば生(しょう)を愛すべし。存命の喜び、楽しまざらんや」と返すようにしている。
生(しょう)・愛してますか?
(カエル先生高橋宏和ブログ2016年1月11日『医師と死生観』http://www.hirokatz.jp/entry/2016/01/11/023245を加筆・再掲)