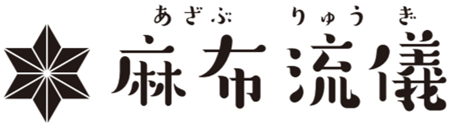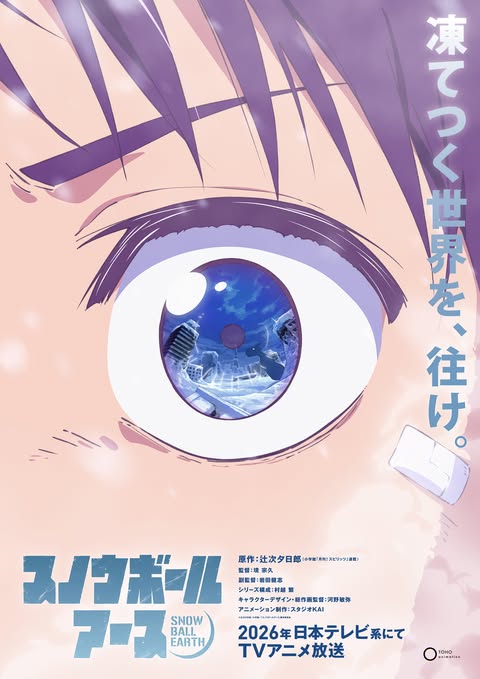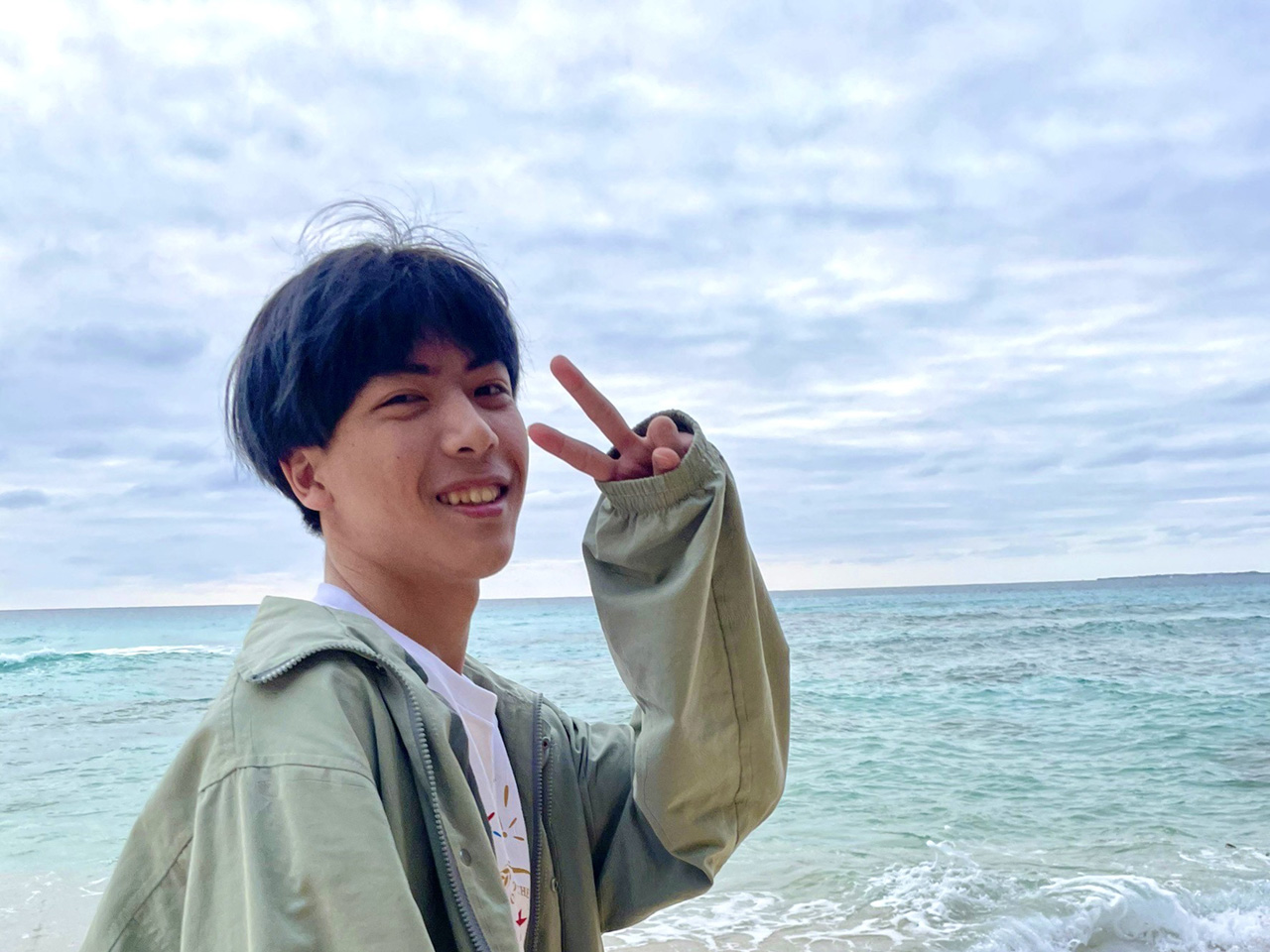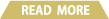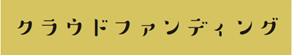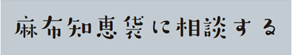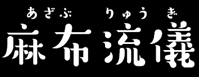好きを主軸に。

FIND/47 より 熊本県 水田
最近歳下の医学生と話す機会を得た。
彼らが口々に言うのは、「将来なに科医になるのがいいか迷ってて。AIとかもあるし、逆に手技のある外科とかのほうが生き残りやすいのかなって」だ。
医学生というのは、6、7年の大学時代に全ての科を学ぶ。医学生時代には専攻みたいなのはない。
今は大学卒業後2年間の研修期間があるが、昔は大学卒業の時に専攻する科を決めて教授のところに弟子入りのお願いをしに行った。医局に入る、いわゆる入局というやつだ。
将来なに科になるか悩む期間も増えたし、医療以外の分野で活躍する医師免許持ちもいるから選択肢も増えた。
選択肢が増えると、人間というのは逆に決められないものだ。
ましてやわが国の保険診療分野は先行き不透明。
僭越ながらアドバイスするとすれば、究極的には「好きなことをやれば」になる。
理由はいくつかある。
まず第一に、未来は完全には予測できない。
AIが進歩して内科医の代わりを務める日も来るだろうが、それがいつかはわからない。
世の中の風向きが変わって、AIは電気を喰うからやめようとなるかもしれない。
AIは個人情報をデジタルデータ化してグローバルに処理するわけで、その気になれば世界中のどこからでも誰かの個人情報(や会社の情報とか)をぶっこ抜ける状態だからやめようとなるかもしれない。
要は、外部要因というのは完全には予測不可能であり、しかも複数因子、マルチファクターが複雑怪奇に絡まり合うならなおさらである。
だが、「好き」という内部要因はそうそう変わらない。
だから予測不可能で可変な外部要因に基づいて未来を決めるのではなく、予測可能で可変性の低い「好き」という内部要因に基づいて未来を決めるのがよいのではないか。
〈最善の未来予測は、それを発明することだ〉(アラン・ケイ)
いくつか思うのは先人たちのことだ。
たとえばiPS細胞研究の山中先生は、当初整形外科医としてキャリアをスタートさせた。
残念ながら整形外科医は向いていなかったようで、基礎医学に転向し偉業を成し遂げたわけだが、重要なのはノーベル賞受賞者ですらキャリアスタート時には自分に何が向いてるかはわからないということだ。
あるいはスタジオジブリ宮崎駿監督。
今でこそ「世界のミヤザキ」として尊敬されているわけだが、あの人も外部要因が別であればまた評価も変わっていたかもしれない。
宮崎駿監督のキャリアの中で、アニメというものに対する世間的評価が逆風だった時代もある。
「アニメが犯罪を誘発する」みたいな世論があと一歩強く、アニメが強力に規制されていたら、宮崎駿監督は悪の親玉みたいな扱いだったかもしれない。
重要なのは、もしそんな状況でも、宮崎駿監督は地下にもぐって少女を主人公としたアニメを作り続けただろうということだ。
「好き」という内部要因は、強い。
わが国の保険診療分野は先行き不透明で、若き医学生が悩むのも無理はない。
だがその中でも「好き」を原動力に、未来を切り開いていってもらいたいと思う。
〈先が見えないからといって途方に暮れることはありません。どんなに自信を失っているときでも、その中でも自分にできることが必ず何かあるはず。〉(ショーン・ケイ)
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年11月10日を加筆・修正)