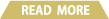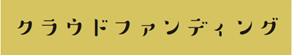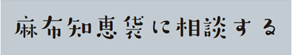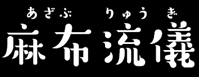厚生労働省『人生会議』ポスター炎上を機に確認する日本の死生観(前編)
2019年11月、厚生労働省が『人生会議』啓発のために作ったポスターが「炎上」した。
『人生会議』とは、<もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のこと>(①:厚生労働省HPより)である。
今回の『人生会議』もそうだが、延命治療や終末医療の議論になるとよく、「日本には宗教がないから、無意味に延命する」的な意見が出る。それに引き続いてその場にいるみんながそうだそうだとうなづくシーンを何度となく経験するが、ぼくは内心そのことに反発を感じていた。
以前からつらつら考えていたことをここでいったんまとめてみたい。いつの日かきっちり文献的に裏付けを取ろうと思っていたけど、done is better than perfect、まずはやってみたい。間違ってるところがあれば直しますので。
宗教を横文字で言えばreligionで、religionの語源はre(再び)+ligare(縛る、結びつける)で、地上に産み落とされた無数の孤独な魂を再び結びつけるのが宗教だ。
さて、宗教のない民族などいるものだろうか。
狭い意味での宗教には教祖、教義、教団が必要だが、もっとうっすらとした、むしろ信仰とか宗教「感」とでも呼ぶべきものは当然日本にもある。
そしてその信仰・宗教「感」は実は医療のあり方にも大きく影響を与えている、というのがぼくの仮説だ。
特に終末期医療に絡む部分を順不同で書いてみる。ぼくが興味があるのは事実であり価値判断ではないので、これこれこうだからいいとか悪いとか、こうすべしと言いたいわけではないことをあらかじめ述べておきたい。
・「死は穢れ」ー極力遠ざけておきたいもの、死
死に対する感覚について、『古事記』に有名な黄泉の国の記載がある。
国つくりの神、イザナミノミコトは火の神を生んだことで死んでしまう。
夫であるイザナキノミコトはそれを悲しみ、黄泉の国に迎えにいく。イザナミノミコトは「私はすでに黄泉の国のものを食べてしまった身で本来は帰れない。だが黄泉の国の神に頼んでみましょう」と言ってイザナキノミコトを暗闇の中で待たせる。しかしイザナミノミコトは待ちきれなくなって闇の中で火をつけると浮かび上がったものは
<蛆たかれころろきて、頭には大雷(おほいかづち)居り、腹に黒雷居り、陰に拆(さき)雷居り、左の手には若雷居り、右の手には土雷居り、左の足には鳴(なり)雷居り、右の足には伏(ふし)雷居り、あはせて八はしらの雷神成り居りき。>(『古事記』岩波文庫 1963年 p.28-29)
すなわち蛆だらけ、雷(いかづち)だらけの変わり果てたイザナミノミコトの姿であった。それにしても雷だらけである、黄泉の国。
イザナキノミコトはほうほうの体で逃げ出すのだが、ここに見られる黄泉の国はじとっとして真っ暗でいやーな感じである。国つくりの神イザナミノミコトですら、『古事記』の中では死後「天国」とか「極楽浄土」とかには行けない。
神道では死は穢れであり、この世は浮き世で清浄なものという感覚があると聞く。
こうした感覚、現世が素晴らしく、死んだら暗くてじめじめしたいやーなところに行くというフィーリングは、たぶん今も終末期医療・延命治療の在り方に影響していて、そのために出来るだけ長くこの世に留まるのがよいというスタイルの医療が行われているのではないだろうか。
・孤独死はなぜ嫌われるー臨終・見送りは大事
基本的に、人は皆、死ぬときは一人だ。少なくとも物理的には。
だが、21世紀になってもなお孤独死は大きな社会問題とされるのはなぜか。
波平恵美子『日本人の死のかたち』(朝日新聞社 2004年)によれば、日本では今もなお、<(略)人はできるだけ多くの人に見送られて死出の旅立ちをするのがよいとする信仰が、まだ人びとに強く支持されている(略)>(p.54)。
「親の死に目に会える/会えない」というのは日本人にとって大問題だ。家族が患者さんの死出の旅に立ち会えるよう、家族が来るまで心臓マッサージを続けた経験のある医者は少なくないはずだ。
そこに医学的な意味は無いけれど、文化的・宗教的な意味はあって、そんなことも日本の延命治療や終末医療のありかたに影響している。
臨終が大事という感覚は、特に法然以前の「逝き方」に見ることができる。
源信の『往生要集』では、極楽浄土に逝くためには臨終のときにどんなことをしなければならないかが事細かに書かれている、らしい(そのうち読みますので…)。
特に臨終の場に同心同行、同じ信心を持った者がいてあげるのが大事で、一部ではそれが多ければ多いほどよい、みたいなところもあったようだ。
ここらへん、今も残る「たくさんの家族や友人に見守られて死ぬ」「盛大な葬儀で見送る」という理想の死に方と同根ではないだろうか。
ちなみに法然は、臨終よりも<平生の念仏行こそが肝要である。(略)平生に念仏を修し、その教えを信じている者は、臨終行儀をする必要はない。>とおっしゃっているそうです(浄土宗総合研究所『共に生き、共に往くために 往生と死への準備』平成24年 浄土宗)。
・復活の教義がないースパゲティシンドロームと油山事件、ギロチン、解剖
終末期医療を考えるときに対比されるのは欧米である。
曰く、「欧米では日本のように濃厚な延命治療はしない」、「日本には宗教がないから“無駄に”延命治療する」。
日本にも宗教「感」はあり、それが終末期医療のありかたに影響を与えているというのがぼくの仮説だ。
欧米と比べ、日本の宗教「感」にないのは復活の教義で、それが大きく終末期医療のありかたを左右しているのではないか。
ちょっと脱線してクイズ。
次の2つのうち、どちらが非人道的に残酷で、どちらか文化的で尊厳が保たれているか。その理由は。
A.ギロチンによる斬首刑
B.電気椅子による死刑
答えはAのギロチンによる斬首刑が非人道的で、電気椅子による死刑のほうが文化的。
理由は、ギロチンで首を斬られると「最後の審判の日」に復活できないから。
戦時中に、アメリカ兵捕虜十数名を日本兵が日本刀で斬首し、戦後に「残虐極まりない」とされた油山事件というものがある。処刑は軍法会議にのっとって行われたものだったが、その処刑方法がまずかった。
自らもキリスト者である佐藤優はこう述べる。
<では、この事件のどこに問題があったのか。日本は裁判にかけて、軍の手続きをとって、無差別爆撃という国際法に違反した行為を行ったとしてから、アメリカ人を銃殺にすれば問題なかったのです。しかし、日本刀で首を切り落としてしまうというのは、「残虐な行為」「捕虜虐待」になります。
さらにここでのポイントは、文化が関係してくるということなんです。つまり、イスラム諸国でもキリスト教国でも同じですが、死者の復活が教義で定められています。首を切ってしまったら、最後の日に復活ができませんね。ですから、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教文化圏では、首を切り落としたり火葬にしたりするのは禁じ手なんです。「いくらなんでも復活できないほど悪いことはしていないだろう」というのが一神教文化圏の一般的な感覚なんですね。>(佐藤優・高永喆『国家情報戦略』講談社2007年 p.130)
上記の佐藤優氏のキリスト教、ユダヤ教、イスラム教文化圏では、火葬にするのは禁じ手という話について、2019年7月ころのtwitterでも、イスラム圏では火葬は忌み嫌われるというやりとりがあった(②)。
この復活の教義があることが、欧米の終末期医療をあっさりとしたものにしているのではないかというのが10年来のぼくの仮説である。
つまり、最後の審判の日になれば互いに復活して再会できる、とか、延命のために多くのチューブなどが身体にとりつけられる「スパゲティシンドローム」では復活の日にミゼラブルである、という潜在意識が、欧米の終末期医療の姿を規定しているのではないか。
10年ほど前からそんな仮説を抱いているのだが、不勉強ゆえ立証できてはいない。
日本でも禅宗では「大死一番、絶後蘇息」なんて言って、死んでから再生するみたいな言い方もあるようだが(中村圭志『信じない人のための<宗教>講義』みすず書房 2007年 p.121)、どうも原始キリスト教の復活の教義のほうはもっとリアルで肉感的、マテリアルな肉体が復活すると信じているようで、そこらへんはかなり医療のスタイルにも影響しているんじゃないかなあ。
日本の場合にはそんなリアルな感じで復活を信じているというのはないようで、だからこそ終末は永遠の別れとなり、少しでもその別れを先延ばしにしたいというスタイルの終末期医療につながっていくのではないだろうか。
ではどうして日本で復活の教義が生まれなかったのかというと、これはひとえに気候風土のせいだと言えよう。
高温多湿だとほら、いろいろと腐るから。
参考HP①https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html