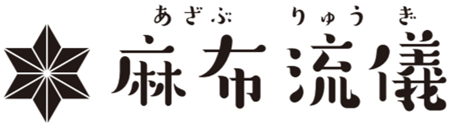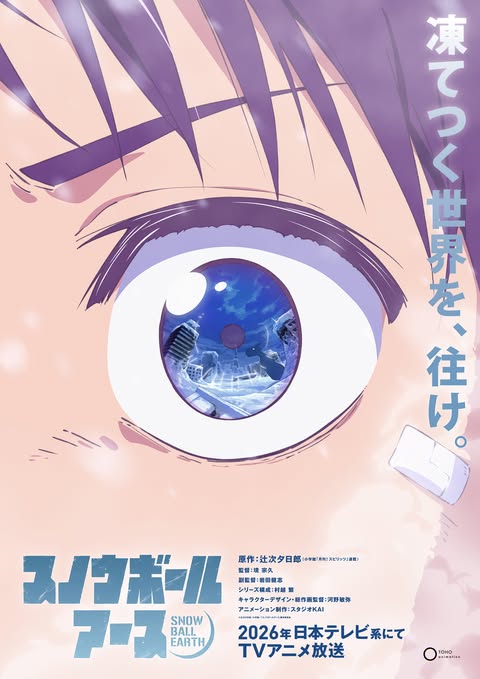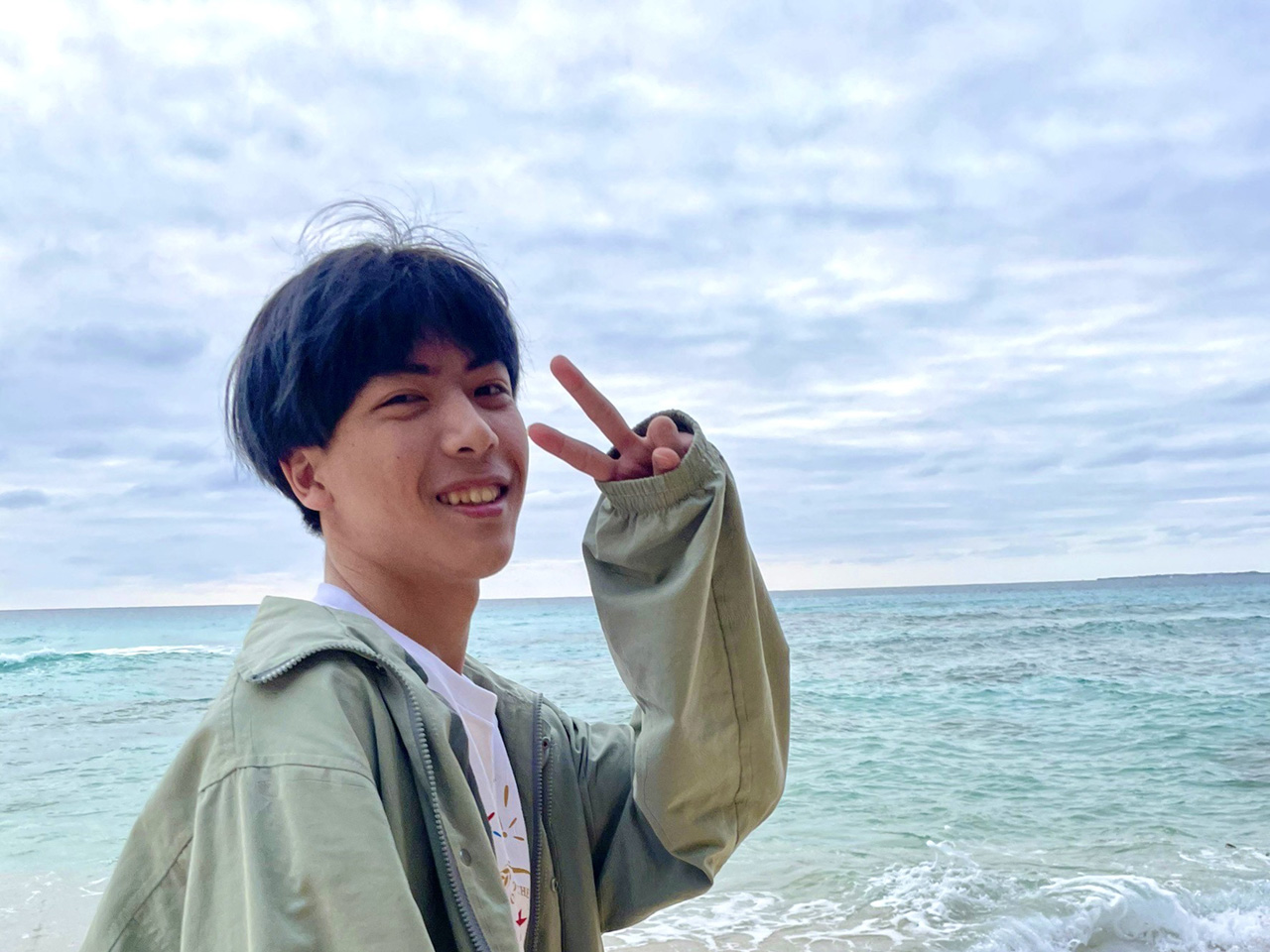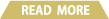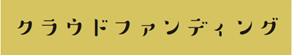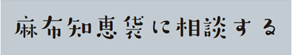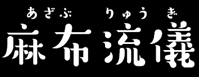不易と流行、古典と現代。
不易と流行の不易に触れたくて、細々と古典を読んでいる。
原著で読めるほどの力は無いから邦訳や解説書を読むのだが、多くの古典の名著の母国語訳が千円から数千円で手に入る出版大国・日本には心から感謝である。

photoACより
わからぬながらも古典を読んでいると、数千年前の人が考えた思想や言葉が、時を越えて胸に刺さるのを感じる。名著の名著たるゆえんだが、数千年前に吐かれた言葉の矢が現代人の心に刺さるなんてことが、なぜ起こるのだろうか。
古代の賢人たちの個々の素晴らしさはひとまず置いておくとして、まずはこうしたことが考えられる。
数千年から一万年近くの人類の歴史のなかで、ほんとうに無数の思想や言葉が生み出された。
その中で後世の多くの人に刺さる思想や言葉だけが生き残った。
刺さらぬ思想や言葉は忘れ去られたからら、残った思想や言葉は立派なものだけとなった。思想や言葉の生存バイアスである。
そしてまた、つらつら考えるに、生き残る思想や言葉というものは、人間の身体性に根ざすものが多い気がする。
どんなに社会体制が変わっても科学や技術が進歩しても、人間の身体性はあまり変わらない。
朝になれば目が覚めてなんだかんだと動き回る。動き回れば腹が減る。腹が減って飯を食えば美味かったりまずかったり。腹一杯になれば眠気にも襲われるだろう。
長い年月には恋をしたり学んだり学んでも忘れたり、そうこうしているうちに歳を取って老いて死んでゆく。
そんなのは何千年も変わらない。
人間の愚かさダメさ賢さ尊さの多くは、心も含めた身体から生まれいづる。
そんな変わらぬ身体に基づき出てくる様々な事象が絡まり合いそれぞれの時代は織りなされる。だから数千年前に吐かれた思想や言葉が身体性に根ざしたものであれば、現代人にも刺さる可能性が高まる。
もっとも、科学や技術により身体性も拡張するから少しずつ事情は変わってくる。
身近な例でいえば、数十年前なら「あの人はなんでも知っていて、まるで“歩く事典”だね」みたいな褒め言葉はまだ使われていたが、どこにいても一瞬であれこれ検索できるようになったネット時代はそうしたことは言われなくなった。記憶力や知識と言った脳の機能が、ネットにより拡張したおかげである。
これからも様々な身体機能があれこれ拡張し、それによって語り継がれる古来の思想や言葉も変わってくるだろう。
だがまあ変わらないのは、どんな状況になっても我らは生きていかねばならぬということだ。
you know,
dum vivimus vivamus、
生きている間は、生きようではないか。
(古代ローマのことわざ。
ヤマザキマリ・ラテン語さん『座右のラテン語』SB新書2025年 p.150。一部改変)
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年1月31日より加筆修正)