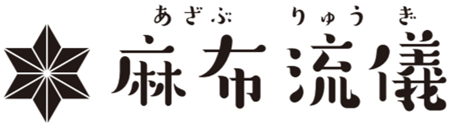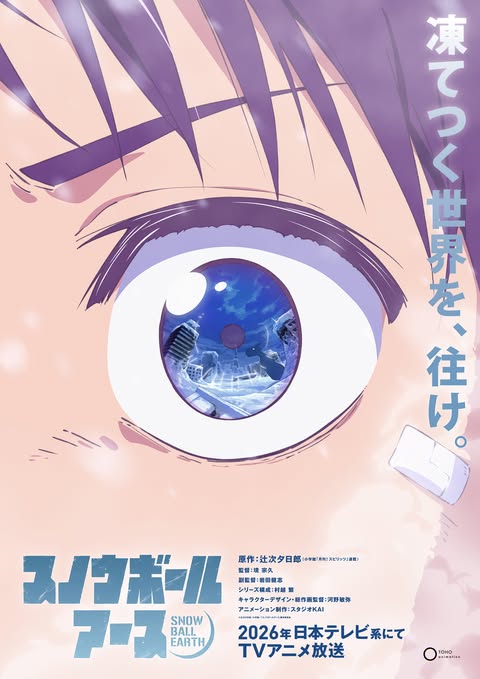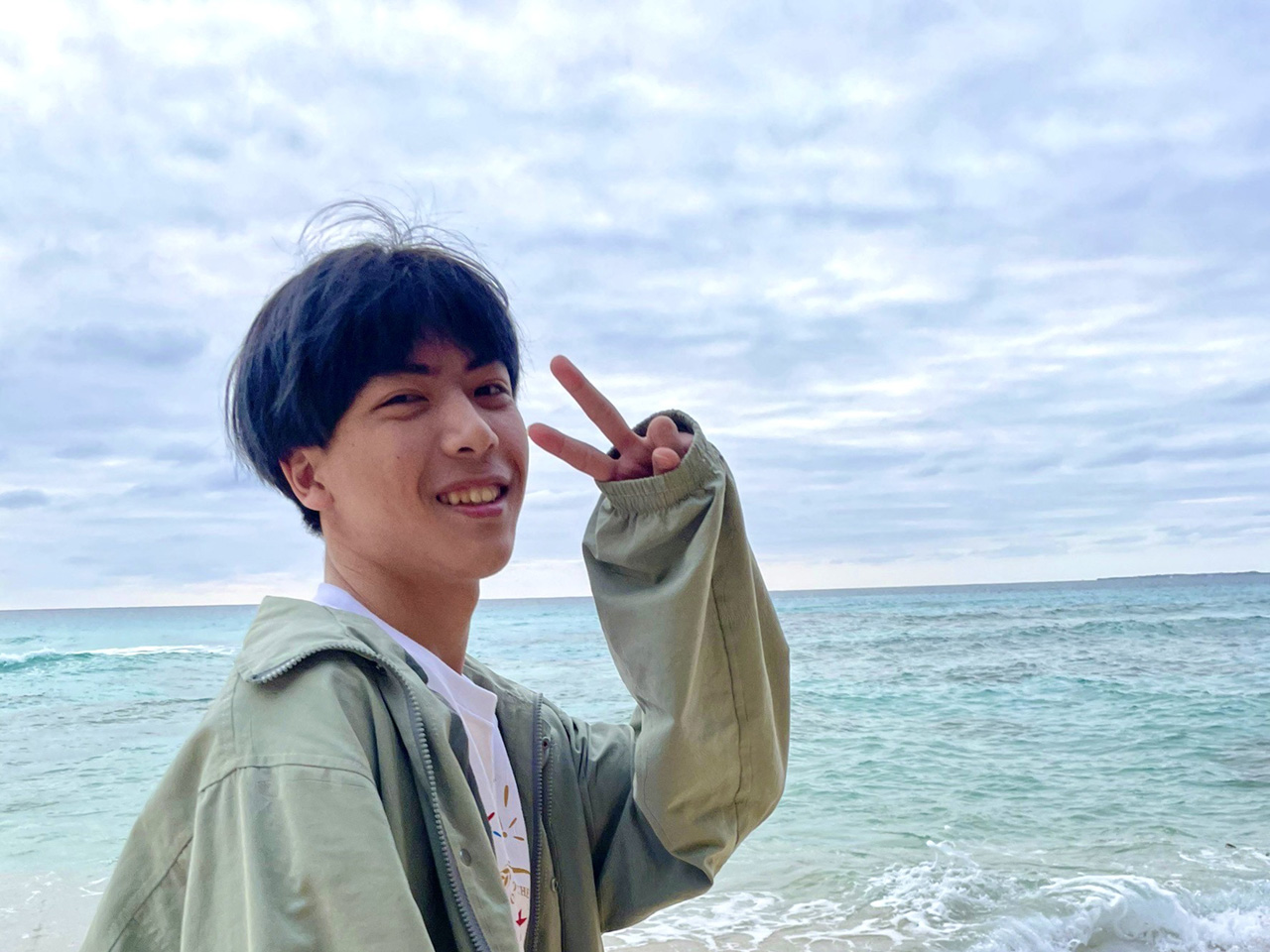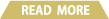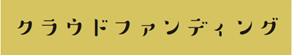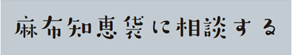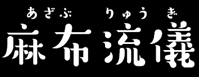「ねたみ」考。
およそ世の中のモノには良い面悪い面両面あって、一見悪いことのように見えても別の面から見るとポジティブな働きをしていることもある。
「怒り」などはその代表で、怒ってる人を見るとまわりはおっかないけれど、悪や不正に対する「怒り」もある。そうした義憤や公憤が社会悪を克服する原動力となることもあるので、「怒り」の感情は実は大切である。
だがしかし、一個だけ悪い面しかない感情がある。
それはねたみの感情、「怨望」である。そんなことを福澤諭吉が書いている(福澤諭吉・著、齋藤孝・訳『現代語訳 学問のすすめ』ちくま新書二〇〇九年 p.163-175)。
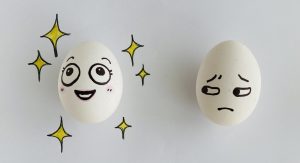
photoACより
ねたみの感情は、ただひたすらにネガティブだ。
〈怨望は、働き方が陰険で、進んで何かをなすこともない。他人のようすをみて自分に不平をいだき、自分のことを反省もせずに他人に多くを求める。そして、その不平を解消して満足する方法は、自分に得になることではなく、他人に害を与えることにある。〉(上掲書 p.165)
個人的には、空を飛ぶ鳥を眺めて暮らす日々でこのねたみの感情というのはどこかへ行ってしまった。「鳥のヤツらは飛べていいなあ」とねたんでも仕方のないことで、ただ捕まえて羽根をむしって喰うだけである。
このねたみの感情がなぜ生まれるか。福澤諭吉はこう分析する。
〈(略)怨望は貧乏や地位の低さから生まれたものではない。ただ、人間本来の自然な働きを邪魔して、いいことも悪いこともすべて運任せの世の中になると、これが非常に流行する。〉(p.168)
「親ガチャ」などという言葉が日常的に使われ、ねたみがあふれるSNS時代にこの言葉を思うと味わい深い。
いつの世も生まれついての不公平はゼロにはならないが、それでもなお自助努力で多少はなんとかなる仕組みにしておかないと社会にねたみが蔓延するのだろう。
ねたみの生まれにくい社会にするというのは為政者に任せるとして、個人としてはどうするべきか。
まず第一に、「ねたまないようにする」というのは机上の空論である。そんなのムリっす。
ねたみという感情の悪いところは、不平を言うばかりで行動に移さないことである。だから行動に移す。
もちろん「無敵の人」路線はいけない。
だがねたみの対象となる人をよく観察し、そのねたみの源、専門用語でいうところのネタミゲンを研究する。
そうしてネタミゲンの良いところをマネしたり、悪いところをマネしないようにする。
万物すべてを我が師と考えるのだ。我が師にも教師と反面教師がいるので、どうぞお好きなほうをお取りください。
自分の人生は自分のものなので、より良い人生を送れるようねたみすらなんらかの原動力にしてしまうしかないだろう。
合言葉は、「こ・の・ね・た・み・は・ら・さ・で・お・く・べ・き・か」である。メラメラメラ。
(『カエル先生 高橋宏和ブログ』2025年1月20日を加筆・修正)