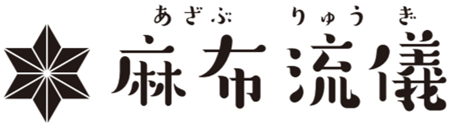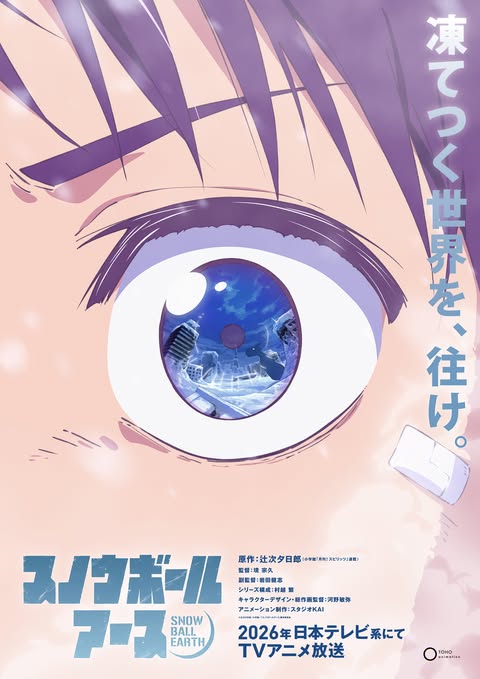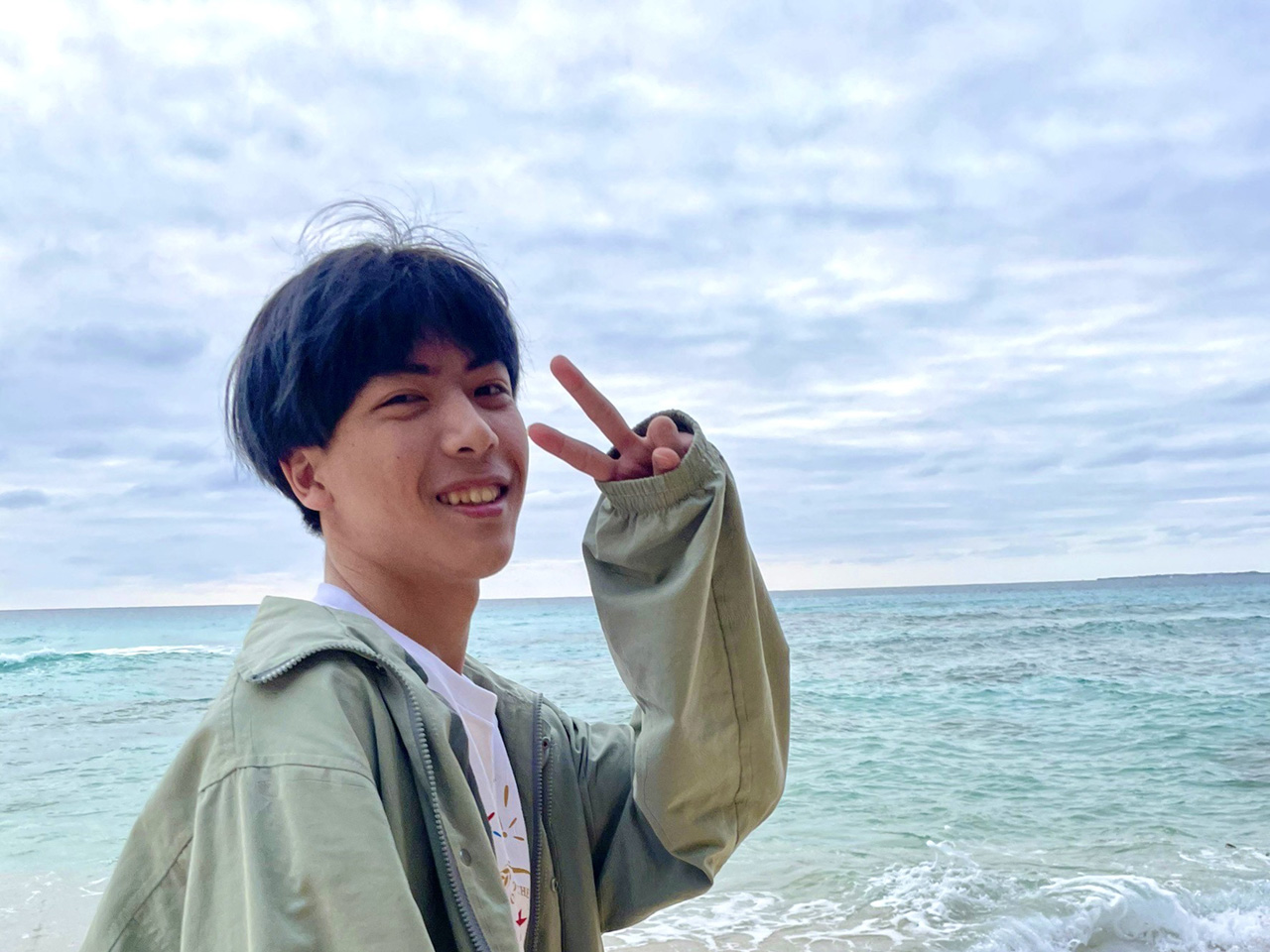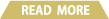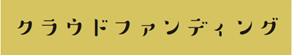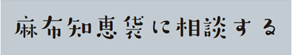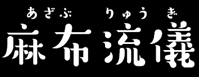「終活」があれば「中活」もある。
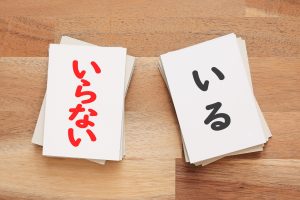
photoACより
「終活」というものがあるならば、「中活」というものもあるのではないか。そんなことを考えた。
wikipediaによると、自分の人生の終末に向けていろいろと整理をする「終活」という言葉が考えられたのは2009年だという。その年の週刊朝日で終活の特集記事が数ヶ月に渡って組まれた。
ありのままを書くと、いわゆるミドルエイジ・クライシスとどう付き合うかがこの数年のテーマだ。
自分はこれからどう生きていったものか。そんなことを考えるなかで、齋藤孝氏のこんな言葉に出会った。
〈(略)私は50歳になって、本を捨てられるようになりました。これまで相当な量ーおそらく何千冊という単位ーを手放してきました。〉(齋藤孝『50歳からの孤独入門』朝日新書 平成30年 kindle版80/138)。
齋藤孝氏ほどの多読多作の方でも、50歳の若さで蔵書を整理し始めるのかというのが驚きであった。
これを読んで積極的に身の回りの細々としたものを整理し始めたのが数ヶ月前。実に多くの発見があった。
やや偏執狂的に、毎日毎日少しでもいいからものを捨てる。本一冊CD一枚、はるか昔いただいた名刺一枚チラシ一枚でもいいから毎日捨てる。
そんな日々を送っていると、たしかにココロの健康によいのである。
スピリチュアルなことを抜きにして考える。
昔、滋賀県の工場で暑さのなかロクセラム・アムマットの粉塵に悩まされながらジンキーを塗っている頃、工場のラインが故障で止まるたびに身の回りの掃除を命じられた。
「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5S活動というヤツで、当時はラインが止まったら休ませてくれよと思ったがあれはあれで意味がすごくある。
今パーソナル5S活動をしてみると、隙間時間に整理整頓をし続けると、忙しい時の探し物が減る。
なにしろ物が減ってるから、大事なものがすぐ見つかる。
また、5S活動のウラの目的は、ヒマな時間を無くすと余計なことを考えたりしなくなるというのもあるのであろう。
思えば自衛隊の富士学校に体験入隊した時も、スキマ時間があれば常にブーツを磨くよう指導されたものだ。
人間、ヒマな時間が出来ると余計なことを考えて悩んだりする。
また、モノを整理して捨てていくと、不必要なものに時間と気力を取られなくなるとともに、整理の過程で取っておくべき「自分が本当に大切にしたいもの」を再発見する。
認知症のケアの中で「回想法」というのがあって、これは認知症患者さんの過去を積極的に振り返ることでアイデンティティを確認してココロの安定を図るというものだが、ものを整理する過程で「自分が本当に大切にしたいもの」を再発見することで同じような効果があるのだろう。
終末期にはまだ早い中年期に、さまざまなものを整理整頓して人生後半戦に備える、中年期活動、略して「中活」というのもあるのではないか。
そんなわけで、これからミドルエイジ・クライシスを迎えられる皆様におかれましては、「中活」というのをしてみてもよいかもしれません。
〈どのように靈魂がその肉體に住んでいるか見たくおもうひとは、どのようにその肉體がその日常の住居を使用しているか觀察するがよい。つまり、住居に秩序がなく亂雑である場合には、その靈魂の支配する肉體も無秩序で亂雑であるだろう。〉(『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上)』岩波文庫p.58)
住居を整え肉体を整えることで、ココロを整えるやり方もあるのだろう。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年8月1日を加筆修正)