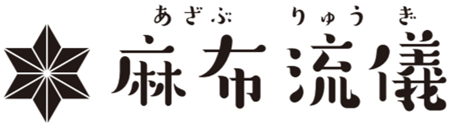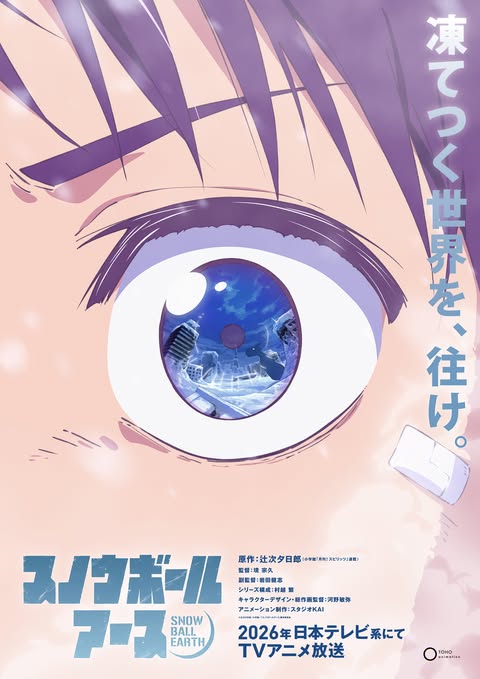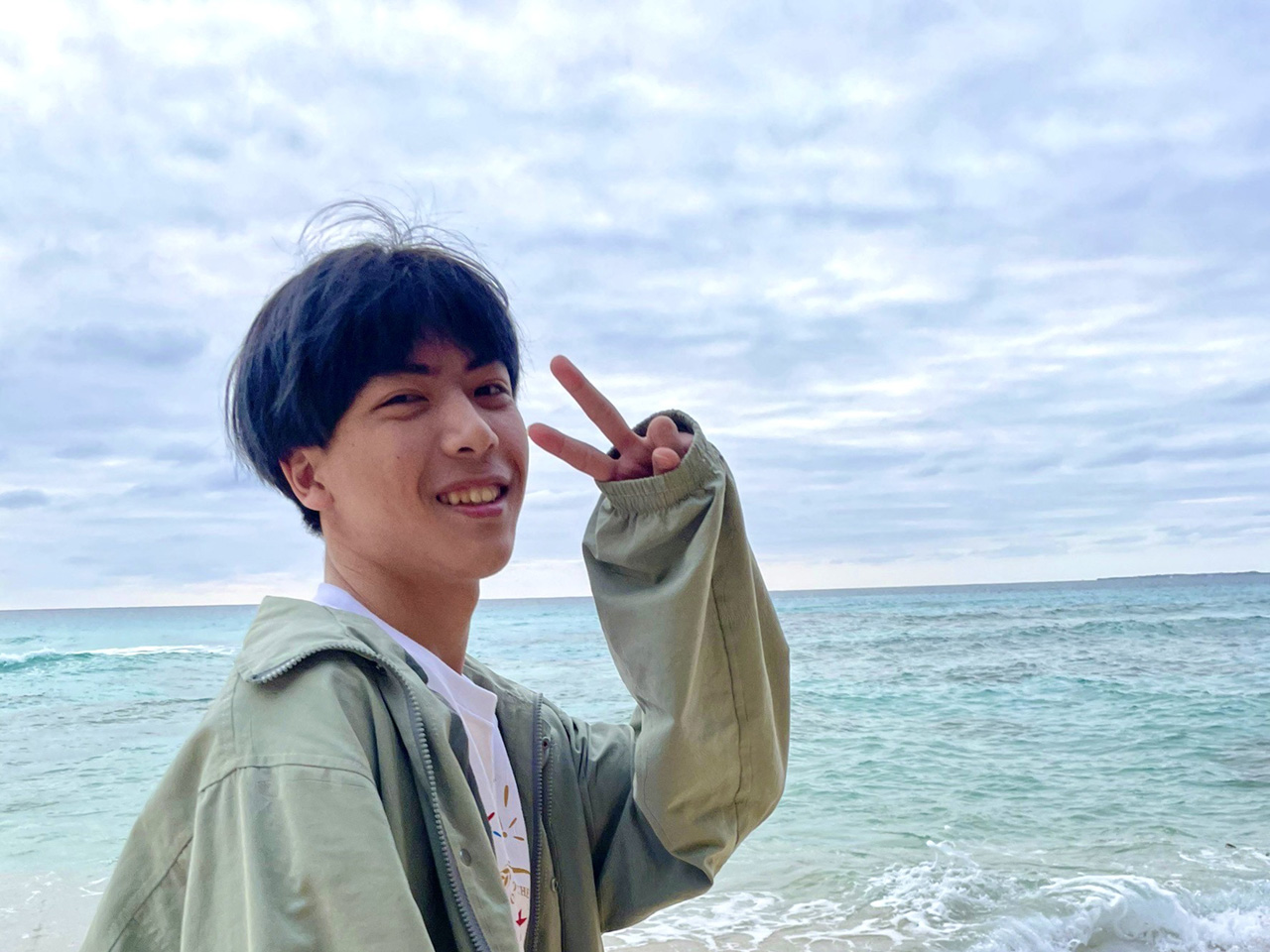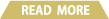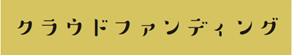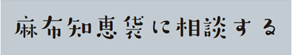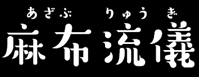ライフワークは人生100年時代の最善の生存戦略である(その1)

photoACより
ライフワーク、ライスワーク、ライクワーク
「ぼくね、人間にはライフワークとライスワークがあると思うんですよね。人生を通して取り組むのがライフワーク。んで、ごはんを食べるためにやるのがライスワーク。ダジャレですけど。あと、好きだからやるっていうライクワークもあるかな。
ライフワークとライスワーク、それからライクワークも、一致してればいいけど一致してなくてもいい。ライスワークやりながらごはん食べて、じっくりのんびりライフワークに取り組んだってええんやないかと思うんですわ」
そんなことを聞いたのは、大阪の淀川を行く屋形船の上であった。
<エリック・エリクソンは、人間のライフサイクルの最後の段階は「統合」を達成すること、つまり人生の過程で成し遂げてきたことや達成できなかったことを、自分自身のものとして主張できる意味のある物語として結び合わせることを含んでいると考えた。>(M.チクセントミハイ『フロー体験 喜びの現象学』世界思想社 1996年 p.166)
人生は前半で“発散”し、後半で“収束”する。
7、8年前まで大学生だったつもりでも(ほんとにそんな感覚なんです)、すでに47歳になってしまった。仮に「人生100年時代」が本当だとしても、現在47歳のぼくは、“収束”のフェイズに入りつつあることになる。マンマ・ミーア。
40歳を越えたころから人生の有限性を体感するようになった。
何でもかんでも首を突っ込むのもいいけど、その場合、あちこち駆けずり回ってすり減って、結局なんにも形にならないということにもなりかねない。
何かワンテーマに我が有限なる時間と気力を振り分けて、ライフワークとしてやっていったほうがよいのではないかなと思っている次第である。
ライフワークやライフテーマを持って生きている人は、強い。
ごはんを食べていくライスワークで右往左往し前進後退を繰り返しながらも、ライフワークやライフテーマがあれば人生の「軸」や「芯」や「プリンシプル」が持てるので、一貫した人生を送れる。
もしライフワークとライスワークが一致すればそれは最高だが、そうでなくてもライスワークで生活の糧を得ながらライフワークを少しずつやっていけば、迷い少なく楽しく生きていけるのではないだろうか。
ほら、オタクやマニアやコレクターって、楽しそうじゃないですか。
人生100年時代の、仕事
〈こころよく 我にはたらく仕事あれ
それを仕遂げて 死なむと思う〉(石川啄木)
死ぬ気もないし死にたいとも思わないが、仕事にもいろいろある。
生きる糧を得るための仕事や行きがかり上やらざるを得ない仕事もあれば、生きていく気力を与えてくれる仕事もある。
生きる糧を得るための仕事と生きがいになる仕事が一致すれば素晴らしい職業人生だが、一致しなくても構わない。
生きる糧を得るための仕事をライスワーク、生きがいになる仕事をライフワークと呼んで、そんなことを教えてくれたのは大阪の街づくりをライフワークにしている人だった。
歴史を振り返るとライスワークとライフワークが別だった人というのはたくさんいる。
遺跡発掘をライフワークとし、そのための費用を稼ぐために実業を行なったシュリーマン(諸説あり)もいれば、若くしてライフワークとなる(はずだった)詩作に出会いながらも、その後(後世の人からみれば、だが)ライスワーク中心の人生に移ったランボー。
アインシュタインは特許庁の仕事をしながらライフワークである物理学の論文を書いていた。
近年でもリーナス・トーバルズはライフワークであるLinuxの開発マネジメントを生きる糧を得るライスワークとは分けて行なった。
ライスワークしながらライフワークを行なった人は何も偉人ばかりではない。
淡々と日々の仕事をこなしながら郷土の歴史を調べてまとめ、後世に残すような地域の知識人は古今東西たくさんいるし、そうした人たちが積み重ねた郷土史は歴史家たちにとって宝石のように貴重なものになったりする。
だから、生きる糧を得るライスワークと生きる目的となるライフワークが全然別でも構わない。
実際に、前述のランボーなどは振れ幅が大きい人生で、ライフワークである詩人を卒業した後は骨太な実業家として生き、それでも飽き足らず常人離れしたトレーニングののちに筋骨隆々としたベトナム帰りの軍人として敵を倒しまくった。ウソですけども。
中年クライシス
中年クライシス、ミドルエイジクライシスというものがある。
人生の中年期や、現役引退期に襲ってくるもので、突如として「いったい自分は今まで何をしてきたのだろう」「自分がやりたかったことっていったい何なのだろう」「自分とはいったい何者なのだろう」という思いにとらわれる、自己一体感の悩みだ。「ああお前はなにをしてきたのだ…」と吹き来る風に問われるひとときが、中也ならずとも人生にはあるのだ。ゆやんゆよん。
クライシスというくらいなので、中年クライシスとは劇的かつ深刻なものとなることがある。
河合隼雄は中年クライシスの相談にくる人についてこう書いている。
<これらの多くの人は大なり小なり抑うつ症的な傾向に悩まされる。今まで面白かった仕事にまったく興味を失ってしまう。あるいは、何もする気がしなくなる。そして、重いときには自殺の可能性さえ出てくる。>(河合隼雄『中年クライシス』朝日新聞社 1993年 p.9)
中年クライシス、ミドルエイジクライシスは一言で言えばアイデンティティが揺らぐときである。アイデンティティとは自己同一性だ。自分が今まで自分自身であり、今このときも自分自身であり、これからもまた自分自身であり続けるという確信こそが、自分という存在の安心感のキモなのだから、それが揺らぐのはさぞ恐ろしいことだろう。
アイデンティティの構成要素の中に、「自分は何をしていた/いる人か」というものがある。一貫したアイデンティティを保つためには一貫したワークを持つのが有用だ。
それこそがライフワークだ。ライフワークを持つことは、人生100年時代を乗り切る最善の生存戦略なのだ。
ライフワークとライスワークを分けることは、時として有効な生存戦略となる
生存戦略としてライフワークをみたときに、生きる目的であるライフワークと生きる糧を得るライスワークが別であることは、時にプラスに働くことがある。
ライフワークとライスワークが一致すれば幸せな職業人生であるのは間違いない。
だが、ライスワークは構造的に外部依存的であり、自己コントロールが利かない部分がある。
非常に現実的な話をする。
ライスワークでは、生きる糧である報酬や評価は自分以外の外部からもたらされる。
どれだけ良い仕事をしても、自己以外の外部が評価してくれなければ報酬は得られずごはんが食べられない。
想像していただければわかるが、一次産業だろうが二次産業だろうが三次産業だろうがそれは同じだ。
また、金銭的報酬以外でも、政治分野であれば選挙に落ちたり政争に敗れればライスワークとしての仕事を手放さなければならない。
会社だって配置転換や人事移動があるし、景気という外部条件でライスワークとしての仕事が失われることもある。
いわゆる「土地持ち」で不動産収入で食っている人でも、人口減少社会では店子も減るし、天災や戦争で全てを失うこともある。
報酬や境遇が外部事情により左右されるライスワークでは、自己コントロールできない部分が、度合いの差はあれど残ってしまう(現実問題としては、その自己コントロール率の多い少ないの度合いこそが重要なのだが)。
アイデンティティの根幹をライスワークに求めることの危険性はかくのごとくであり、ライスワークと別にライフワークを持つメリットはここにある。
ライスワークは外部依存的であるがゆえに時に脆弱である。
生きる糧を得るライスワークの外部依存性をほぼゼロにするには、究極的には光合成でもしながら生きるしかない。
というわけで、ちょっと葉緑素を移植してくる。
(続く)