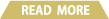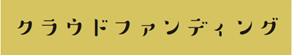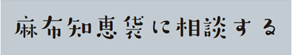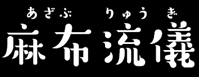日本ほめ上手列伝
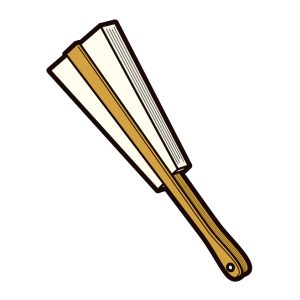
(toraneko6さんによるイラストACからのイラスト)
常々思っていることだが、日本には、「ほめ」が足りない。
ネットやテレビでやってる「日本SUGEEE、世界がしびれる、憧れるゥッ!」的なやつじゃなくて、普段づかいのやつ。
ネットでは「いいね!」を乱発するくせに、日常生活で「いいね!」を使いこなしているのはクレイジー・ケン・バンドくらいではなかろうか。
日本には、「ほめ」が足りない。
足りないものには値札がつく。
普段からひとにほめられていないから、「ほめ」を求めてオジサマたちは夜な夜な街をさまよい歩く。夜の蝶から「さすが~」「知らなかった~」「すご~い」「センスい~」「そうなんですかぁ」の「ほめ」のさしすせそを手に入れるために、彼らは大金を払うことを惜しまない。嗚呼、巧言令色鮮し仁。
しかしそんなほめが足りない日本にも、燦然と輝くほめ上手たちがいる。もしほめ上手を目指すなら、そんなほめ上手たちから学ばない手はない。
日本のほめ上手といえば太鼓もち、幇間(ほうかん、たいこもち)。
夜のお座敷の雰囲気づくりのプロ、幇間の歴史は長い。
そもそも「たいこもち」という名前は、豊臣秀吉の側近曾呂利(そろり)新左衛門がしょっちゅう「太閤、いかがで、太閤、いかがで」と言って太閤秀吉を持ち上げていたから「太閤もち」→「太鼓持ち」というようになったという説があるくらいだ(諸説あり。小田豊二『悠玄亭玉介 幇間の遺言』集英社文庫 1999年p.28)。
ちなみに幇間というのは酒間を幇(たす)けるという中国の言葉からきている(同書同頁)。
さて、最後の幇間と呼ばれた悠玄亭玉介が、こんなことを言っている。
とにかく相手に惚れてみな、と。そしてそのためには
<あたしはね、とにかくまずお客様の顔を見ることにしてた。
目とか鼻とかおでことか、じーッと見る。そうすると不思議だね。いいところが見つかるんだよ。人間てのは、不思議なもんで、どんな人でも二カ所はいいところがある。目つきがいいとか、口に愛嬌があるとか、鼻がかわいいとかさ。顔じゃなくたって、笑い声が子供みたいだとか、姿勢がいいだとか。
もちろん、金払いがいいってえのが、あたしにとっては最大の魅力だけどね。>
(上掲書 p.260)。
どんな人でも二カ所はいいところがある。一カ所と言わないところが粋ですね。
87歳まで活躍した玉介は<人に惚れ、仕事に惚れ、自分に惚れる。それがあたしの長生きの秘訣よ。>(p.289)とも言っている。
よく見て言葉を発する職業といえば小説家。
小説家井上光晴を追ったドキュメンタリー映画『人間小説家』の中で、よく思い出すシーンがある。たしか、こんなシーンだった。
井上光晴がお弟子さんの女性とチークダンスを踊る。そこはかとなく色気が漂う。
女性は六十前後くらいだろうか。
女性がインタビュアーに語る。
「先生はね、私のことほめてくださったの。耳たぶが可愛いって」
そういいながら女性はほんのり頬を染める。
「今までそんなこと言ってくれる人なんていなかったから。でもね、何十年も前……亡くなった両親がそう言って私をほめてくれた。耳たぶが可愛いって。誰にも言ったことはなかったけど」
ほめの一言が幸せな子供時代をよみがえらせ、女性のモノトーンの日常をフルカラーに変えたのだ。相手をよく見、言葉を選びぬき心を射抜く。まさにほめの達人と言うべきであろう(1)。
ちょっとひねった「ほめ」もある。
サッカー日本代表の監督だったイビチャ・オシム氏は数々の名言で知られる。
オシムは選手に対しても辛辣で厳しい言葉を浴びせ続けたが、それだけではなかった。
<「ずっと厳しいことを言っておいて、ふとした時に、ポンと『もうワールドカップ出場を狙っていないのか』とか、『もっと上を見いいんだぞ』とか、声をかけるんです。例えば阿部やいろいろな選手に、お前たちは代表の選手に劣っている部分はそんなにないんだから、もっと上を見ていいんだと、言ってくれたりするんです。(略)」>(木村元彦『オシムの言葉 フィールドの向こうに人生が見える』集英社インターナショナル 2005年 p.203。「 」内は羽生直剛選手談)。
世界が誇る名将にぼそっと「もっと上を見ていいんだぞ」と褒められたら、選手も発奮するというものだ。
ちなみに、オシムは<「言葉は極めて重要だ。そして銃器のように危険でもある。(略)新聞記者は戦争を始めることができる。意図を持てば世の中を危険な方向に導けるのだから。ユーゴの戦争だってそこから始まった部分がある」>(『オシムの言葉』p.38)とも語っている。
「引きのほめ」というのもある。
あえて語らないことで成立する「ほめ」だ。
政治評論家の三宅久之氏は阿川佐和子氏と会うたびに
「これはこれは。また今日は一段と……」
とだけ挨拶するという(阿川佐和子『聞く力』文春新書 2012年 p.242)。
そのエピソードについて、阿川氏はこう続けている。
<でもたしかに、「一段と……」のあとに、実のところ何が続くかはわからないのですが、言われた側としては、「一段と、おきれいで」とから「一段と若々しく」とか、そんなふうに褒めていただいたような錯覚を起こすものです。三宅さんとしても、本人を前に、歯の浮くような具体的な形容詞を使わなくて済むから、さほど負担にはならない。>(上掲書同頁)
なるほど。
日本の歴史の中で、ほめの金字塔といえばやはり淀川長治だろう。
一定以上の年代の人なら知らない人はいない映画評論家で、一言でいえば愛の人だ。
映画への愛、映画人への愛、視聴者への愛にあふれた淀川氏の映画解説には、「ほめ」しかなかった(2)。
「どの映画にも見所はある」が信条で、日曜洋画劇場でくりひろげられる映画解説では、どんな映画であっても決してけなすことはなかったという。たとえB級C級映画であっても彼は必ずほめるところを見つけ出してほめた。
ぼくたち「ほめ」業界の間で伝説となっている映画解説がある。
こんな感じだったようだ。
「はいみなさんこんばんは。今日の映画は、『大蛇アナコンダ』。あなたね、大蛇、出てきますよ。出てくるヘビがね、なんと、体長、5メートルも、あります。大きいですね、すごいですね、怖いですね。しかもね、アナコンダ、とても速い。くねくねくねくね、動くんですね、速いですね、すごいですね、怖いですね。 ね、あなた、なんといっても、アナ、コンダ、大きいですよお、楽しみですねえ。それではじっくりお楽しみください」(3)
大蛇が大きいとしか言っていないのだが、よっぽど大きい蛇だったのだろう。
淀川氏は89歳まで長生きしたが、この人もまた人に惚れ、仕事に惚れ、自分に惚れた人の一人だったのかもしれない。
日本のほめ上手たちを振り返ってみたが、どの達人たちもかなりの人生経験を経た人々であることに気づく。「ほめ」の達人になるには、まずは自分の人生の達人にならなければならないのだ。
ほめ上手への道は長く険しいが、それでも明日はモア・ベター。
いやあ、「ほめ」ってほんとうにいいものですね。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。
(1) 映画を見たのは二十年以上前で、あえてうろ覚えのまま書いた。大きく間違ってたら直します。
(2)ただしイベントなどでは結構辛口なことも言っていたようだ。
(3)youtubeで『アナコンダ』の解説があがってないか探したが見つからなかった。残念。どこで見られるかご存じのかた、教えてくださいませ。