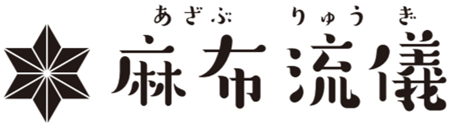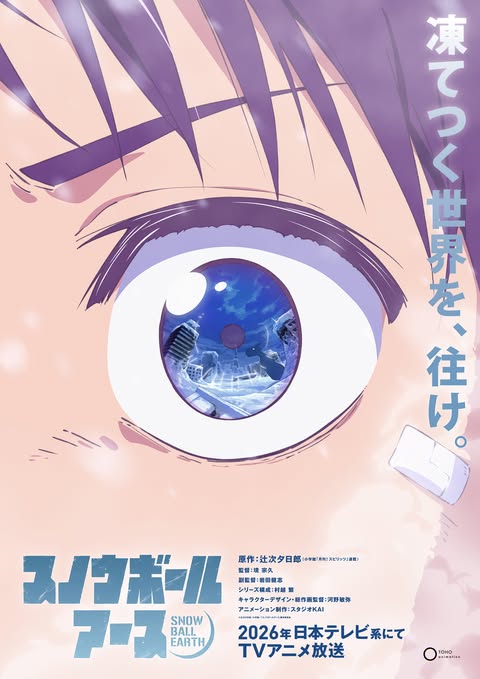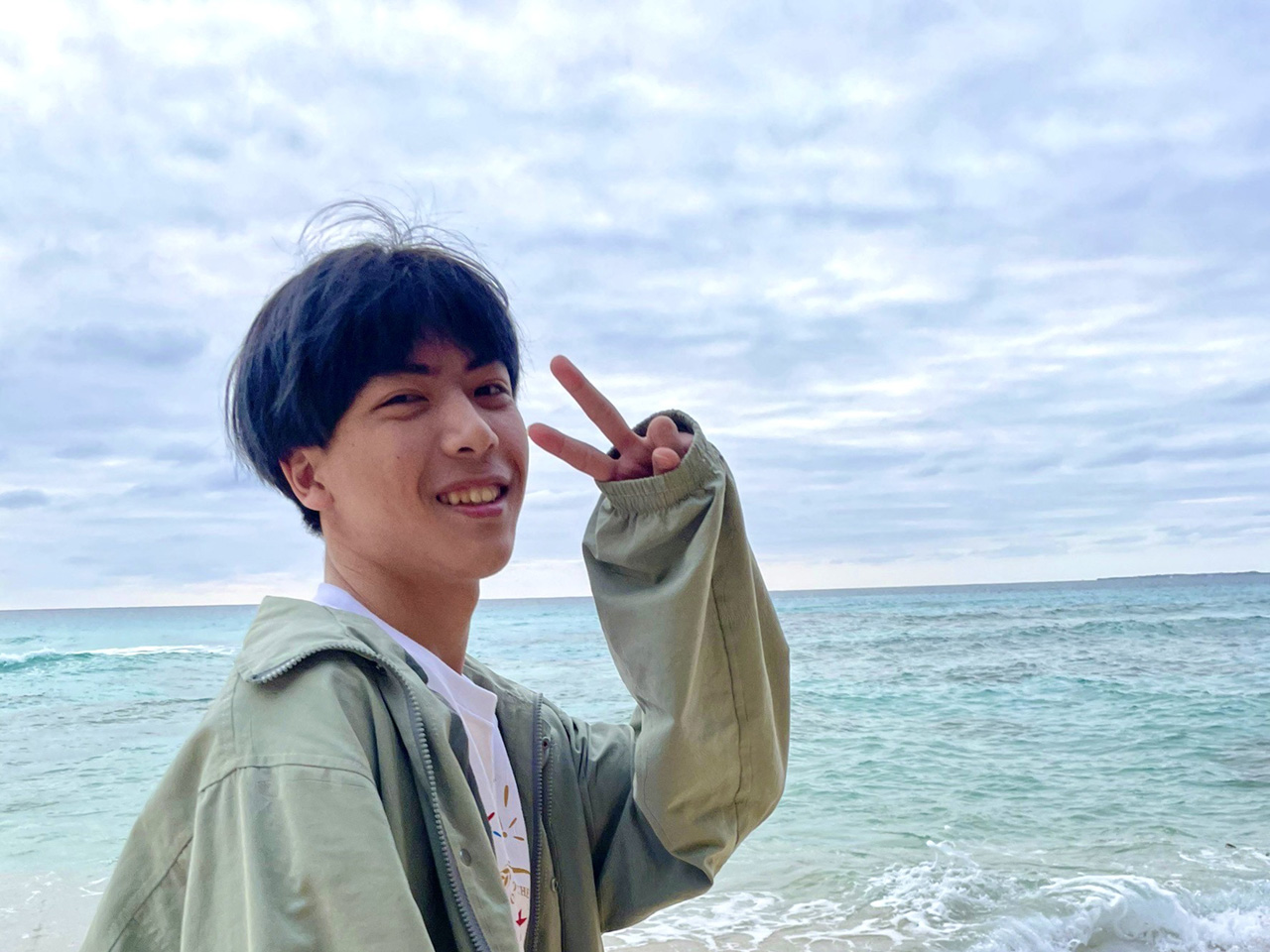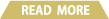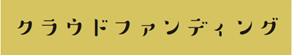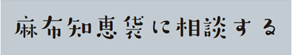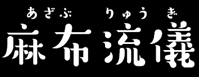因果と縁。
「原因と結果。因と果で因果。
仏教では、因と果のほかに“縁”というのもありましてね。
因と果の間に“縁”があると考えます」
とある僧侶から聞いた。
その話を聞いたときは、「縁とか言い出したらなんでもありやんけ」と思った。仏罰が当たるといけないから黙っていたけど。
だが不思議なもので、月日が経つにつれて、なるほど“縁”というのはあるのかもしれないなと思うようになった。
“縁”とはなんだろうか。
オカルト的なもの、スーパーナチュラルなものをできるだけ排して考える。
つらつら考えるに、“縁”とはランダム性かもしれない。
生命を細菌やウイルスから守る免疫機構の一部である抗体は多種多様で、その数はどう考えても遺伝子の組み合わせより多いという。
なぜ有限な遺伝子の組み合わせの数を超えて、無限に近い抗体が作り出されるかは長年に渡り医学のナゾの一つだった。
それに対しアンサーを出したのが利根川進氏で、遺伝子と抗体は一対一対応ではなく、遺伝子がある程度ランダムに組み合わさって抗体の設計図となることで、多くの組み合わせが生まれるのだという。
医学生時代に授業で聞きかじった話で、なにしろ劣等生だったから記憶もあいまいだ。
将来この麻布流儀のネタになるってわかっていればもっとしっかり授業を聞いていたのだが仕方がない。なにしろその頃はまだ麻布流儀は無かったからな。
遺伝子の組み合わせという“因”が、抗体という“果”を生み出すまでに関与するランダム性。これが“縁”ということではないか。
名作映画『おくりびと』の原案である青木新門氏の小説『納棺夫日記』。
映画『おくりびと』を因果の“果”とすると、『納棺夫日記』は間違いなく原因である“因”である。
『納棺夫日記』が無ければ、『おくりびと』は生まれなかった。
だが、『納棺夫日記』という“因”があれば、必然的、自動的に『おくりびと』は生まれただろうか。
『納棺夫日記』はお読みいただければわかるとおり、非常に地味で内省的、後半は物語の形から離れ、いわば哲学的モノローグとなっている。
当初、『納棺夫日記』は自費出版に近い形で世に出され、初版は500部から2500部程度であったという。
そんな形で世に出た、いわば地味な一冊の本がまわりまわって1人の読者の手に届く。本木雅弘氏である。
インドへの旅の中で生と死を見つめた若き本木雅弘氏は、友人から勧められてこの本を手に取り、その一節に心をつかまれた。
<蛆を掃き集めているうちに1匹1匹の蛆が鮮明に見え始めた。畳を必死で逃げている蛆もいる。柱をよじ登っているやつまでいる。蛆も命なんだ。そう思うと蛆たちが光って見えた>
本木雅弘氏は、その後何年もかけて周囲を説得し、『おくりびと』を映画化した。
500〜2500部という限られた本が世に出、それが一人の読者に届くというのは“縁”であろう。
もしあの時、この本でなくほかの本を本木雅弘氏が手に取っていたら、と思うと、“縁”というものの一部はやはりランダム性な気がする。
そしてまた、“縁”というのはランダム性だけではない。
『納棺夫日記』を映画化したい、という本木雅弘氏の強い意志が無ければ、やはり『納棺夫日記』という“因”は『おくりびと』という“果”は生まれなかっただろう。
というわけで、因果を結ぶ“縁”。
縁というのは、ランダム性と人間の意志ではないかと思った次第である。
それではまた。良い1日を。
縁があったらお会いしましょう。
(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2025年10月17日を加筆・修正)