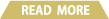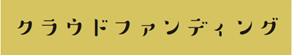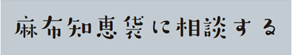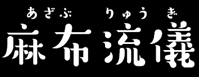「命がけの医療のお仕事ありがとう」に対する町医者の2つの告白。
コロナ禍の中で医者稼業をしていると、時折「命懸けのお仕事ありがとう!」と声をかけていただくことがある。
その時はありがたくお言葉をいただくが、二つばかり告白しなければならないことがある。小さな告白と大きな告白だ。
小さな告白のほうは、ぼく自身が身を置いているのは町のクリニックであり、コロナとの戦いとの最前線ではないということ。よく言っても後方支援のそのまた後方支援といったところで、コロナとの戦いの最前線である中核病院の医療者ははるかに高いリスクを負っている。
もちろん日常診療でヒヤッとすることや後から考えるとゾッとする場面もあるが、励ましと感謝の声はすべて中核病院の医療者に向けられるべきかと思う。
大きな告白については、「命懸け」の医療活動の部分だ。
産褥熱を解明し消毒法を始めたウィーンの医師センメルヴェイス以来、医学は出来るだけ「命懸け」せずに人を救う方法を模索し確立してきた。
手術や診療は、やるほうもやられるほうも出来るだけ「命懸け」にならないほうがよい。
「命懸け」で治療を受けて命を落としてはいけないから、基本的に「イチかバチか」の治療は避けたほうがよい。
また医療者側が命を落としてはほかの患者を救えない。
医療を「命懸け」にしなくて済むような方法の一つがマスクや防護服による感染防止であり、さらにそうした医療器具を使い捨てにするなどの工夫である。
ただ、普段は容易に供給される使い捨てマスクやガウンが医療現場に回ってこなくなるとは想定外であったし、物品が回ってこないことと医療リソース提供能力を超えて次から次へと入院を必要とされる患者が現れるというのがコロナ禍の恐ろしさだ。
通常なら、クロイツフェルト・ヤコブ病など「根本治療のない感染症」を「命懸け」でなく診療する方法論は相当に確立されており、淡々と実行されているものなのだ。
だから、「命懸け」の医療活動は非常事態の表れであるし、あくまで一時的にやむを得ずに行われていることなのである。
また、「命懸け」の部分は強いて言えば診療のプロセスでありアウトカムではない。
プロセスの部分ばかりに注目されると、いつしか手段と目的が逆転して「命懸け」になることそのものを自己目的化して要求されるようになるかもしれない。
このプロセスと目的の逆転はしばしば起こりがちなので注意を要する。特攻隊も被災地への千羽鶴も「ステイホーム強要団」も、プロセスと目的の逆転の構造は共通している。
「額に汗して働くことは尊い。だが、工夫して額に汗しないで、涼しい姿でそれ以上の成果を上げることもまた尊い」と松下幸之助が書いている(『道を開く』収載「働きかたのくふう」)。
命懸けで一人の命を守ることは尊い。だがさまざまに工夫して、命懸けにならず涼しい顔で、より多くの命を守ることはさらに尊いのだ。
(カエル先生・高橋宏和ブログ 2020年5月9日https://www.hirokatz.jp/entry/2020/05/09/074923 より転載)